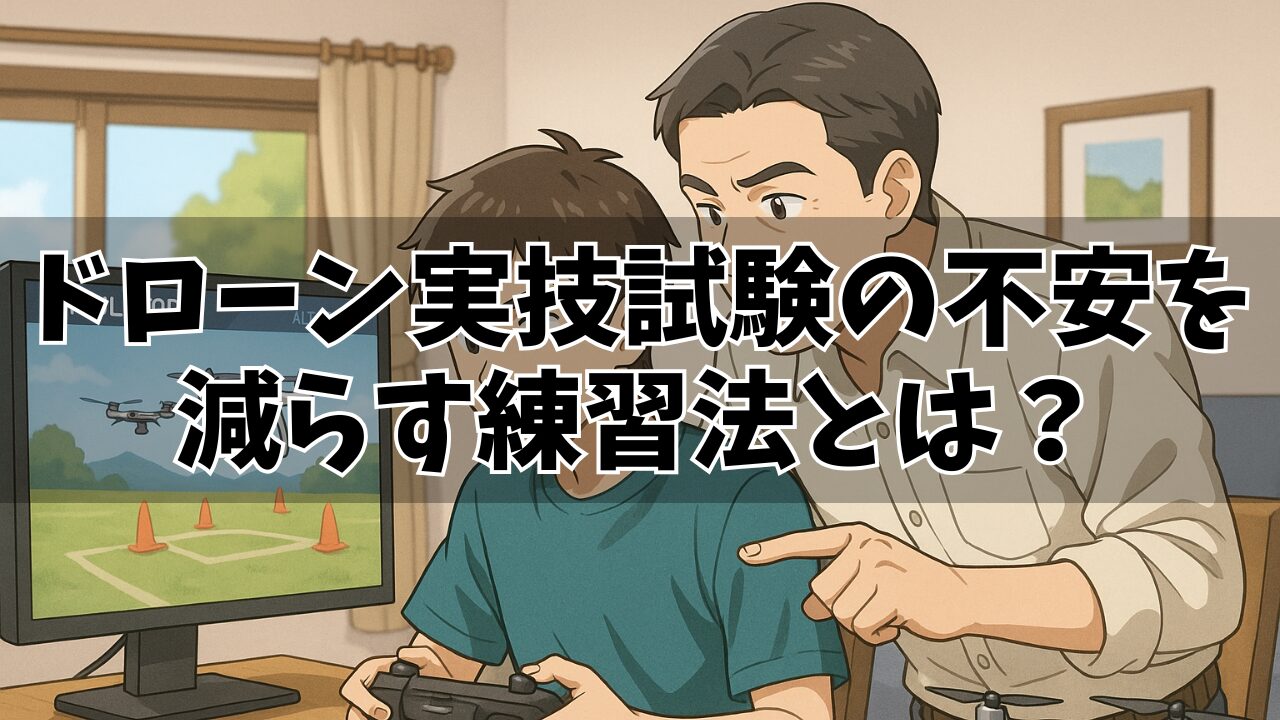「ドローンの実技試験が不安……」そんな声が親子で高まっています。
特に国家資格である二等無人航空機操縦士の実技試験は、初挑戦の家庭にとって大きな壁です。
私自身も、文系出身の父親として初めてドローンに触れたときは、操作どころか設定画面すら戸惑う毎日でした。
しかし、ある無料シミュレーターとの出会いをきっかけに「屋内で練習→河川敷で実地→試験本番へ」とステップを踏むことで、不安を確実に減らしていくことができたのです。
近年は、家庭用パソコンで操作できるシミュレーターの精度が格段に上がっており、実技試験前の“疑似体験”として大いに活用されています。
実技試験では、単なる操縦技術だけでなく「判断力」「安定性」「再現性」が問われます。
そうした要素も、シミュレーターを使えば繰り返し練習できます。
この記事では、
- 実技試験に向けた不安の原因とその乗り越え方
- 具体的なスキルと試験官の評価ポイント
- 家庭でできる段階的なシミュレーター練習法
- おすすめの練習用ソフトとその選び方
- 子どもと一緒に取り組む「10分練習法」の実例
などについて詳しく解説しています。
ドローン実技試験の不安をシミュレーターで克服する方法
初めてドローンの実技試験に挑戦する際、多くの方が「操縦がうまくいかなかったらどうしよう」「子どもに教えられる自信がない」と感じるのではないでしょうか。
そんな不安を軽減する有効な手段が、ドローンシミュレーターを活用した練習です。
我が家でも、まずは親である私が一通りの操作を覚えるため、夜な夜なシミュレーターを起動して練習に励みました。
屋外練習のリスクと初心者に多いつまずきポイント
ドローンの屋外練習は開放的で魅力的ですが、初心者にとってはリスクも多く含みます。
特に以下のようなトラブルがよくあります。
- 風にあおられてコントロールを失う
- 周囲の障害物に衝突する
- バッテリー残量を見誤り、強制着陸してしまう
こうした失敗は、心が折れてしまう原因にもなります。
とくに子どもが「失敗=怖い」と感じてしまうと、練習に前向きになれなくなることも。

私も初めて公園で飛ばしたとき、いきなり木に引っかけてしまい、息子の前で情けない顔をしてしまいました……。
ドローンシミュレーターで得られる操作感と本番との違い
シミュレーターは「失敗しても壊れない」「何度でもやり直せる」環境を提供してくれます。
操作の基本であるスロットル、ラダー、ピッチ、ロールの感覚を体で覚えるには、反復練習が不可欠です。
また、ホバリングや旋回などの挙動もかなりリアルに再現されているため、本番に近い形で感覚を養うことができます。
- 風の影響がないため、外での反応とはやや違う
- 画面での距離感に慣れるまで時間がかかる
- 送信機の操作に若干のラグがある場合もある
このような違いを理解しながら使えば、むしろ「違いを埋める訓練」として活用できます。
親が実践した3ステップ練習法で子どもも安心スタート
我が家では「親が先に習得する」を徹底しました。
以下の3ステップで練習を組み立てることで、子どもにも安心してバトンタッチできました。
| ステップ | 目的と内容 |
|---|---|
| 1:個人練習 | 夜間に親が一人で操作習得。失敗を繰り返しながら感覚を掴む。 |
| 2:同時練習 | 親子で並んで同じ動作を練習。互いにアドバイスをし合う。 |
| 3:子ども主導 | 子どもが主体で操作、親は見守り役。成功体験を重ねる。 |
この流れにすることで、親が操作を理解しているという安心感が子どもに伝わります。
最初は不安そうだった長男も、「お父さんがやってた方法、やってみるね」と、自ら練習に取り組むようになりました。
ドローン実技試験で求められる具体スキルを整理する
実技試験に向けて練習を積むにあたり、「どんなスキルが問われるのか」をあらかじめ整理しておくことはとても重要です。
目標が曖昧なままだと、いくらシミュレーターで練習しても試験本番で力を発揮できません。
ここでは、二等無人航空機操縦士の試験で重視される操縦スキルや、試験官が注目する評価ポイント、そして合格ラインに向けた練習法について具体的に解説します。
ホバリング・八の字飛行などの出題パターンと目的
実技試験の代表的な課題として、以下のような項目が設定されています。
- ホバリング(定点での静止飛行)
- 水平移動(直進・後退・左右移動)
- 旋回飛行(機首を向けたままの回転)
- 八の字飛行(進行方向と旋回を組み合わせた飛行)
これらは単なるテクニックではなく、「意図通りに動かせるか」「安定して操作できるか」を試験官が見極めるための課題です。
特にホバリングは、風のない室内であっても軸がブレやすく、実力差がはっきり表れる部分です。



私もホバリングだけは何度やっても苦手でした。焦ってスロットルを強く握ると、余計に揺れてしまうんですよね。
試験官が重視するチェックポイントと評価基準
試験官が見ているのは「完璧な操縦」ではなく、再現性と安全意識です。
つまり、一度の操作ミスよりも、「毎回同じように飛ばせるか」「急な操作をしていないか」が大切です。
- 指示された位置・高度を守れているか
- ゆっくり・安定した操作ができているか
- 予備動作や確認行動があるか(安全意識)
たとえば、機体の移動を開始する前に周囲を見渡すような動作も評価対象になる場合があります。
これは実践での安全運航を前提とした、現場目線の評価基準なのです。
合格ラインに到達するための目標設定と練習の工夫
我が家では、試験に向けた練習を「スキル別に区切って、段階的に強化する」方法を取りました。
すべての動作を一度に練習しようとすると混乱してしまうからです。
練習の組み立て例は以下の通りです。
| 週 | 重点スキル | 目標内容 |
|---|---|---|
| 第1週 | ホバリング | 5秒間の静止を5回連続成功 |
| 第2週 | 水平移動 | 一定距離を±20cm以内で制御 |
| 第3週 | 旋回・八の字 | 安定した旋回と図形の再現性を確認 |
こうした明確な目標を持つことで、毎回の練習が「できた」「まだ不安」と可視化され、改善点がわかりやすくなります。
その積み重ねが、試験本番の自信へとつながっていくのです。
ドローン操縦に強くなるおすすめシミュレーター3選
実技試験に向けた練習の要となるのが、シミュレーター選びです。
一口に「ドローンシミュレーター」と言っても、その種類や目的はさまざまで、操作感や難易度にも大きな差があります。
ここでは、国家資格対策や家庭学習に最適な3つの代表的なシミュレーターを紹介し、それぞれの特徴と活用のコツを整理していきます。
DRL Simulator:実技試験に近い緊張感を再現
「DRL Simulator」は、世界的なドローンレース団体が開発したシミュレーターです。
もともとはスピードレース向けの設計ですが、繊細なスティック操作や反応速度の感覚を養う点では、国家資格対策にも効果的です。
特に以下のような場面で有効です。
- 狭いルートでの機体操作を練習したい
- 素早いスロットル・ピッチ調整に慣れたい
- 集中力を保ちながらの連続操作に挑戦したい



私もこのソフトで一度レースコースに挑戦してみたのですが、あまりのスピードに思わず息子と爆笑してしまいました。
DJI Flight Simulator:公式環境で操縦基礎を徹底練習
「DJI Flight Simulator」は、世界最大手のドローンメーカーDJIが提供する公式ソフトです。
多くの試験機がDJI製であることを踏まえると、このシミュレーターで得られる操作感は、実機とほぼ同じと言えます。
- DJI送信機との互換性が高く、接続がスムーズ
- GPSあり・なしの操作切替ができる
- 練習中に警告表示が出るため、安全意識も身につく
家庭でじっくり練習したい方には最も現実的で導入しやすい選択肢です。
ただし、ソフトのインストールや設定がやや複雑なので、最初は時間に余裕をもって準備しましょう。
RealFlight:安定飛行と空間認識を磨く学習向けモデル
「RealFlight」は、RCヘリやマルチコプターなど幅広いモデルの練習が可能なソフトです。
操作スピードよりも「機体の傾き・反応」「周囲の空間との距離感」を重視する構成になっており、丁寧な操縦を学びたい親子に適しています。
特に以下のような方におすすめです。
- 飛行姿勢の確認を重視したい
- 複数の天候条件で練習してみたい
- 空間認識が苦手で、落ち着いた動きで練習したい
また、英語表記が多いため、初回設定には多少の慣れが必要です。
ただ、その分チュートリアルや設定項目が細かく、「本格的に学びたい」というニーズにも応えてくれます。
ドローンシミュレーターを快適に使うための準備環境
どれだけ優れたシミュレーターを選んでも、動作環境が整っていなければ、快適な練習はできません。
私自身、最初に中古ノートパソコンで試した際はフレームレートが落ちすぎて「操作の練習にならない」と感じたほどです。
このセクションでは、スムーズにシミュレーターを使うためのパソコンスペック、送信機の選び方、トラブル時の対処法についてまとめます。
シミュレーターソフトをスムーズに動かすためのPCスペックとは
ドローンシミュレーターの多くは3Dグラフィックを使用しており、意外と高いPC性能が求められます。
公式サイトに記載されている「最低動作環境」ではギリギリ動く程度のため、可能であれば「推奨環境」以上を目指すと安心です。
| 項目 | 推奨スペック例 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5(第10世代以降)または同等のRyzen |
| メモリ | 16GB以上 |
| GPU | NVIDIA GTX 1660相当以上 |
| ストレージ | SSD推奨(空き容量50GB以上) |
特にグラフィック性能が弱いと画面がカクつき、操作ミスを誘発しやすくなります。



私はスペック不足に気づかず最初の1週間を無駄にしてしまいました……購入前に公式サイトの条件はしっかりチェックしましょう。
試験対策向けおすすめ送信機の選び方のコツ
シミュレーターと組み合わせて使う送信機(プロポ)も、操作のリアリティに大きく影響します。
ここで重視したいのは「試験で使う機体と操作感が近いこと」と「USBやBluetoothでPC接続ができること」です。
- スティック感度が調整できるモデルか
- DJIやFrSkyなど、試験機体と同じ系統か
- シミュレーターと互換性が明記されているか
安価なモデルでも対応しているものは多いため、予算とのバランスを見ながら選ぶとよいでしょう。
初期トラブル(機体接続・キャリブレーション)の解決法
初回起動時にありがちなのが、「送信機が動かない」「操作がずれている」といったトラブルです。
多くの場合は以下のような初期設定で解決できます。
- キャリブレーション(スティックの初期調整)をやり直す
- ドライバソフトの最新版をインストールする
- USBポートを変更する(干渉を避けるため)
また、YouTubeなどには機種別の接続解説動画も多くあります。
初期設定さえ乗り越えれば、あとは快適な練習環境が整っていくはずです。
実機での練習や本番飛行を安心して行うためには、保険の準備も大切です。
万が一に備えた補償内容や選び方についても、事前にチェックしておきましょう。


親子で実践!毎日10分のドローンシミュレーター練習プラン
ドローン操縦は一朝一夕には身につきません。
だからこそ、毎日の少しの積み重ねが試験合格への近道になります。
我が家でも、親子で「毎日10分練習」を習慣にすることで、自然と操縦に慣れていきました。
このセクションでは、初級〜中級レベルの段階別トレーニング、シミュレーターと実機を併用するスケジュール、練習効果を見える化する方法を紹介します。
週3回から始める段階別トレーニングメニュー(初級〜中級)
まずは「週3回・1回10分」で構いません。
以下のようにテーマを決めて段階的にレベルアップさせていきましょう。
| 週 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 基本操作 | 離陸→3秒ホバリング→着陸を繰り返す |
| 第2週 | 定点移動 | 前後・左右に5mずつ移動して停止 |
| 第3週 | 八の字飛行 | 低速で軌道を意識しながら滑らかに旋回 |
短時間でも「今日はここをやる」と明確に決めることで、集中して取り組めるようになります。



我が家では、練習のたびに息子が「今日は成功率◯%!」と得意げに報告してくれるのが日課になっています。
シミュレーターと実機を併用した効率的スケジュール例
シミュレーターだけで完結するのではなく、週末などに実機での確認練習を組み合わせると効果が倍増します。
以下は一例ですが、家庭の生活リズムに合わせてカスタマイズしてみてください。
- 平日(月・水・金):夜10分間のシミュレーター練習
- 土曜午前:河川敷で実機による課題練習
- 日曜午後:1週間の振り返りとログ記録
このサイクルが定着してからは、親子ともに「来週の課題どうする?」と自然に会話が弾むようになりました。
成長を可視化する飛行ログと振り返りノートの使い方
練習の成果を「見える化」することで、やる気の維持にもつながります。
特におすすめなのが、「飛行ログ」と「振り返りノート」です。
- 飛行ログ:日付・練習項目・成功率・操作時間などを記録
- 振り返りノート:その日の気づき・反省・工夫をメモ
毎週まとめて見ることで、「自分はこれだけ積み上げてきたんだ」という自信にもつながります。
親子で並んでノートを書く時間は、練習そのもの以上に貴重な時間になるかもしれません。
まとめ:ドローンシミュレーターで親子の実技試験合格を引き寄せる
ここまで紹介してきたように、ドローンシミュレーターは単なる操作の練習ツールではありません。
それは親が先に学び、子どもと共に成長するための“共通言語”であり、合格という目標を共有するための“家庭の教室”にもなります。
最後に、我が家の体験から得た2つの気づきをシェアします。
親が先に挑戦することで子どもの不安は激減する
親自身が「できなかったところ」「つまずいた経験」「乗り越えた方法」を言語化できることは、子どもにとって非常に大きな安心材料になります。
そして何より、「お父さんがここまでやったなら、自分もやってみよう」と思えるきっかけになります。



私が筆記試験に受かった直後、息子が「じゃあ今度は俺の番だね」と言ったときは、思わず胸が熱くなりました。
学びの過程を共有すれば合格も“家族の成果”になる
ドローン資格の取得は、親子で1枚ずつ合格証を取るだけでなく、そのプロセスこそが“家族の宝物”になります。
夜の10分練習、週末の公園飛行、ノートに残したふりかえり。
そうした日々の積み重ねが、空撮旅行という新たな目標や、技術への興味を育ててくれるのです。
- 中古トイドローンで自宅練習からスタート
- 無料シミュレーターをインストールして操作感に慣れる
- 家族ミーティングで“親が先に学ぶ”ルールを決める
「子どもがやりたいと言い出したけど、自分は文系で機械も苦手……」
そんな親こそ、今から一歩踏み出してほしいと思います。
資格の取得はゴールではなく、親子で空を共有する物語の始まりです。
無事に試験に合格したら、次にやるべき手続きも忘れず確認しましょう。
合格後の流れや申請方法について詳しくまとめた記事があります。