目視外飛行や夜間飛行でドローンを飛ばすには、どんな許可や手続きが必要なのでしょうか?
「高性能なドローンを買ったけれど、どこまで飛ばしていいのかわからない」「暗くなってから撮影したいけれど、違反にならないか不安」といった声は少なくありません。
特に国家資格(二等無人航空機操縦士)を取得したあとも、こうした飛行には追加の講習や条件が必要になります。
目視外飛行や夜間飛行は、国の定める「特定飛行」に該当し、技術的・制度的に十分な理解と対策が求められます。
だからこそ、正式な講習や申請の流れを把握しておくことが、安全で自由なドローン運用の第一歩となるのです。
この記事では、
- 目視外・夜間飛行が「特定飛行」にあたる理由と具体例
- 追加講習のカリキュラムや流れ・費用の実態
- どのような場面で追加講習が活きるのか
- 受講するかどうかの判断基準や費用対効果
- 将来的に子どもとの空撮旅行へもつながるスキルとしての活用
などについて詳しく解説しています。
目視外飛行や夜間飛行でドローンを飛ばすために必要な追加講習とは
ドローンを使って夜間や見通しの利かない場所で飛行させるには、通常の国家資格(二等無人航空機操縦士)だけでは足りません。
こうした飛行は「特定飛行」に該当し、国土交通省の定める追加講習を修了することで初めて、正式な許可申請が可能になります。
私がこの制度を知ったのは、河川敷での練習中でした。
夕暮れ時、長男が「夕日をバックに撮れたらカッコいいよね」とつぶやいたとき、思わず「でもそれ、法律的にできるのかな?」と疑問を持ち、すぐに調べました。

夜間飛行が法律上どう扱われているかを知らないまま飛ばすと、思わぬ違反や事故につながることもあるんです。
まずは基本の国家資格取得ルートを確認しておくと安心です。
これから挑戦する方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
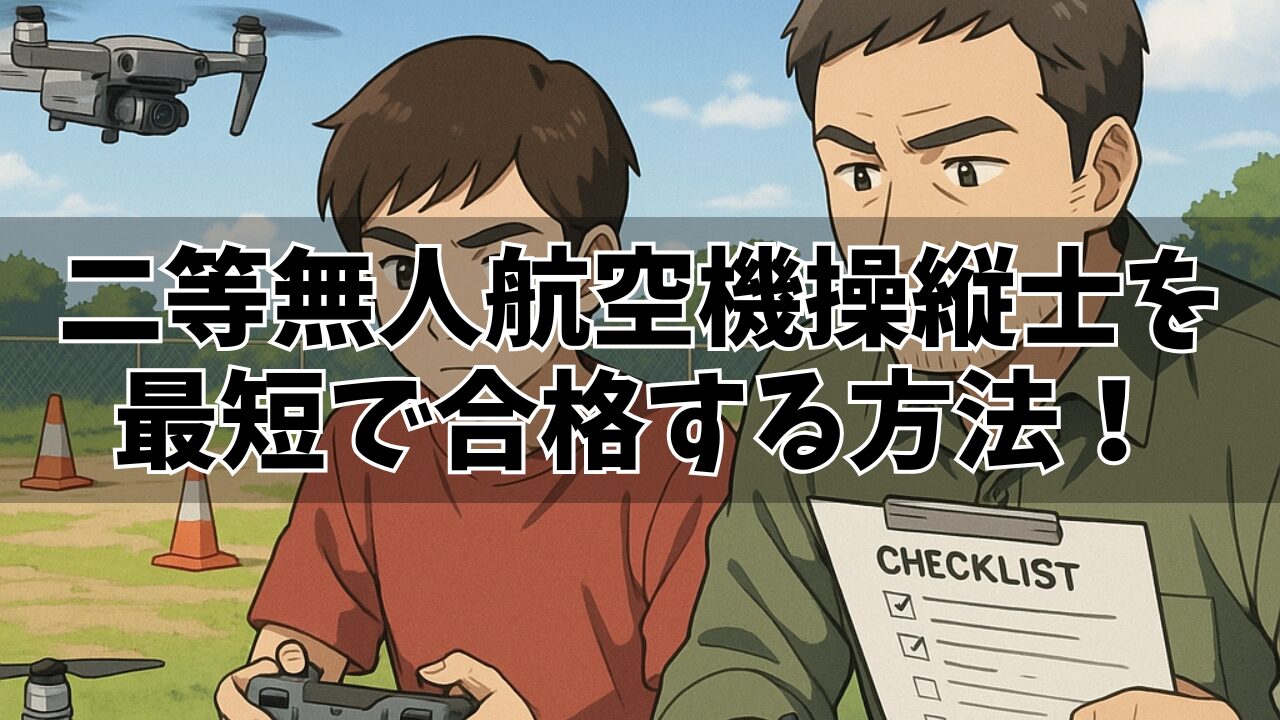
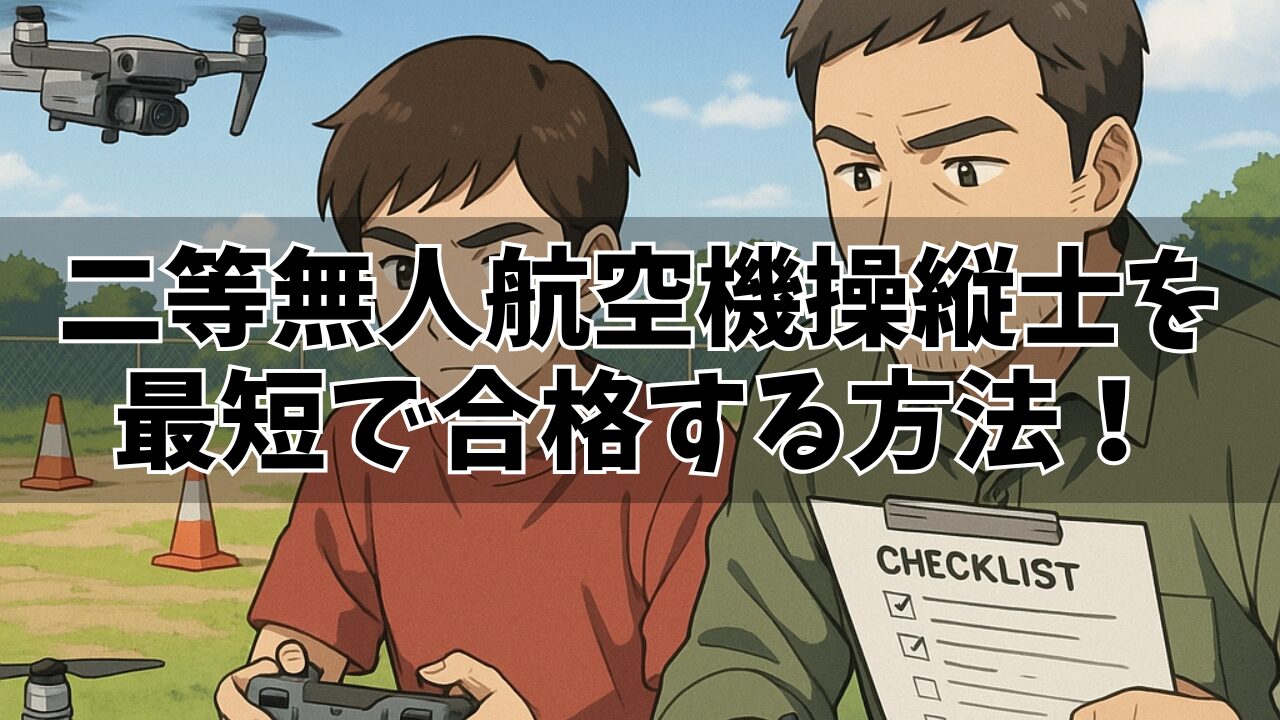
ここではまず、どのような飛行が「特定飛行」にあたるのかを見ていき、その後に講習の流れと実際の費用感についてご紹介します。
夜間飛行・目視外飛行等 特定飛行に該当する具体ケース
特定飛行に指定されるのは、ドローンを安全に飛ばす上でリスクが高いとされる以下のような状況です。
- 目視外飛行(機体が直接見えない場所を飛ばす)
- 夜間飛行(日没〜日の出までの間)
- 人または物件との距離が30m未満の接近飛行
- イベント上空や第三者上空の飛行
たとえば「家の裏山を越えて撮影したい」「近所のイベントで夜景を空撮したい」という希望がある場合、それらはいずれも特定飛行に該当します。
これらの飛行は、事故が起きた際のリスクが高いため、通常の飛行とは別に安全確保の知識と技術が求められます。
そのため、講習修了者でないと申請すらできず、無許可での飛行は航空法違反となる可能性があります。
つまり、「子どもの夢を叶えたい」と思ったとき、まず親が講習を受けて安全・合法な土台を作る必要があるのです。
追加講習のカリキュラムと資格取得までの流れ
追加講習の内容は、通常の技能証明取得と似ていますが、より実務的なシナリオに即した内容になっています。
具体的には以下のような構成です。
- 座学(夜間飛行や目視外飛行に関するリスク・法律・安全対策)
- シミュレーター訓練(夜間や障害物環境での模擬操縦)
- 実地訓練(指導員の監視下で実際に飛行を行う)
これらをすべて修了すると、修了証が発行され、国土交通省のライセンス管理システムに記録されます。
その上で、追加の許可申請を行うことで、夜間や目視外での飛行が可能になります。



私の場合、座学よりも「夜間飛行の実技」が緊張しました。
周囲の光が少なく、距離感がつかみにくくなるので、GPSや画面情報だけが頼りになります。
講習当日の流れや必要な持ち物も、事前に知っておくと安心ですよ。
詳しいチェックポイントはこちらの記事でまとめています。


受講費用と講習対応スクールの選び方
追加講習の費用はスクールによって異なりますが、目安としては以下の通りです。
| 講習内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 目視外飛行講習 | 30,000〜50,000円前後 |
| 夜間飛行講習 | 35,000〜60,000円前後 |
費用面だけでなく、以下のようなポイントにも注目して選ぶのが大切です。
- 国家資格講習と同時に申し込める一貫型か
- 実技場所や夜間設備が整っているか
- 修了後のサポート(申請代行・機体選びの相談など)があるか
地元の認定校だけでなく、宿泊を伴ってでも総合型のスクールに通う価値もあります。
一度の講習が、子どもの将来の自由を広げることになるのです。
追加講習を受けるメリットとドローン飛行の可能性拡張
ドローンの追加講習は「法律を守るためだけのもの」と思われがちですが、実はそれ以上のメリットがあります。
講習を受けることで、飛行範囲や活動の選択肢が一気に広がり、「自分たちにしかできない空撮」や「高単価な仕事」にもつながっていきます。
この章では、私が実感した追加講習の効果と、その後の実際の飛行でどう活かせたのかをご紹介します。
夜間飛行等特定飛行が可能になる
追加講習を修了する最大のメリットは、法律上禁止されていた飛行スタイルが“合法的に解禁される”ことです。
具体的には、下記のような飛行が可能になります。
- 日の入り後の夜間撮影(光量・機体識別を条件に可能)
- 障害物越しの目視外飛行(モニター・ナビ支援使用)
- 長距離空撮や山岳越えなど、直線的な移動飛行
許可を得ていれば、これまで“やってはいけないこと”だった行為が、逆に「できること」としてカウントされるようになります。
この追加講習によって、フライトログや飛行場所の選択肢が一気に広がります。
たとえば、「真夜中の無人キャンプ場空撮」「川の向こう岸の構造物点検」「森の中の探査飛行」などが、実際に“できる”ようになるのです。
自分のライセンスが制限のあるものから、拡張されたものになることで、飛行計画そのものの立て方が変わっていきます。



私は追加講習を終えたあと、「行ってみたい場所リスト」を家族で作りました。
子どもが「夜の花火大会」「温泉街の朝霧」などを提案してくれて、旅先の選び方まで変わってきたんです。
夜間点検・空輸・農薬散布・目視外空撮など高単価案件に参入できる
特定飛行の技術は、単なる趣味の域を超えて、実務や仕事の世界で“武器”になります。
以下は実際に、追加講習修了者が活躍しているジャンルです。
| ジャンル | 主な内容・現場 |
|---|---|
| 夜間点検 | 工場や送電線などの夜間巡回業務 |
| 物流・空輸 | 山間部や島嶼部への医療物資・荷物の運搬 |
| 農薬散布 | 人が立ち入れない夜明け前の田畑への作業 |
| 映画・CM撮影 | 夜間にしか表現できない画角や光を空撮 |
これらはどれも、高リスク・高技術を伴うため、追加講習修了者でなければ参加できません。
一方で、依頼単価は数万〜数十万円と、趣味レベルでは考えられない報酬も期待できます。



私は副業として、知人の農家が発注する「夕暮れの田んぼ空撮」に参加しました。
追加講習修了の証明があったからこそ、信頼されて任せてもらえた案件です。
ドローン追加講習が活きる具体シーンを紹介
追加講習は「制度的に飛ばせる範囲を増やす」だけでなく、現場での応用力としても非常に役立ちます。
この章では、実際の現場で追加講習がどう活かされているのか、リアルなシーン別にご紹介していきます。
商用空撮やイベント撮影における夜間活用事例
夜間飛行の最大の魅力は、昼間には撮れない光と演出が可能になることです。
たとえば夏祭りや花火大会、イルミネーションイベントなどでは、空撮による「俯瞰+光」の映像が圧倒的な訴求力を持ちます。
私が協力した地元イベントでは、灯籠流しの様子を上空から撮影しました。
水面に反射する光が美しく、地上のカメラでは絶対に得られない画が撮れた瞬間、「追加講習を受けてよかった」と心から思いました。



夜間飛行の映像はSNSでの拡散力も高く、動画1本が観光PRの柱になることもあるんです。
インフラ点検・災害時飛行の現場活用
もうひとつ、追加講習が活きる場面が点検や災害対応です。
夜間や視界不良の状況でも、安全に飛行・記録できる技術があることは、自治体や企業からの信頼にもつながります。
とくに、
- 橋梁やトンネルの夜間点検
- 地震・台風後の夜間状況確認
- 山間部・崖下など目視外エリアでの捜索支援
などでは、暗所飛行や遠隔操作が不可欠です。
自治体やインフラ企業と連携する際、追加講習の修了証は「操縦技術の証明」として提出を求められることもあります。
講習を受けた事実そのものが「任せられる人材」であるという評価につながるのです。
こうした場面で活躍するには、制度面の準備に加え、日常の練習・フライトログの蓄積も重要になります。
個人クリエイターの実践応用
もちろん、商業目的だけではありません。
個人で創作活動を行う人にとっても、夜間飛行や目視外飛行のスキルは大きな武器になります。
たとえば、
- 早朝の山頂からの霧映像
- 灯りのない漁港の上空動画
- ドローン短編映画の夜のシーン
など、クリエイティブな映像表現が可能になります。
追加講習を通して得た経験は、YouTube動画・映像コンテスト・企業案件への提案力にもつながります。



私自身、「夜間空撮シリーズ」をテーマにしたYouTubeチャンネルを立ち上げました。
追加講習で学んだ知識が、発信の信頼性を支えてくれています。
ドローン追加講習を受けるべきか迷ったときの判断基準
「追加講習って、結局受けるべきなの?」
これは私自身、資格取得後に何度も考えた問いでした。
費用や時間がかかるのは事実ですが、それに見合う効果が得られるのかは人によって異なります。
この章では、迷っている方に向けて判断のポイントを整理していきます。
ドローン追加講習の費用対効果と回収見込みを試算する
まず冷静に見ておきたいのは「投資対効果」です。
追加講習の費用は概ね5〜10万円程度。
これに対して、どのくらいで“元が取れる”かを簡易的に試算してみましょう。
| 活用内容 | 想定報酬例 | 回収目安 |
|---|---|---|
| 夜間イベント空撮(1本) | 3〜5万円 | 2〜3本で回収 |
| 農薬散布・点検業務 | 5〜10万円/件 | 1〜2件で回収 |
| YouTube収益+案件 | チャンネル次第 | 半年〜1年 |
「受講=即利益」ではありませんが、飛行スタイルの自由度を得られること自体が中長期的な価値になります。



私は最初、「5万円は高いな」と思いましたが、空撮依頼で2回飛ばしただけで回収できました。
自身の目的と飛行スタイルに本当に必要かを照合する
次に重要なのは、「自分のやりたいことに本当に必要か?」という視点です。
たとえば以下のようなケースでは、追加講習を受ける意義が大きくなります。
- 山の向こう側まで飛ばしたい(目視外)
- 夕方〜夜の時間にしか撮影ができない
- 副業や仕事として本格的に取り組みたい
逆に、
- 公園で家族と遊ぶ範囲
- 明るい日中の空撮
- 狭いエリア内の低空飛行
などが主な目的であれば、無理に受ける必要はありません。
そうした方は、まず情報収集やシミュレーター体験から始めてみるのがおすすめです。
制度や訓練の仕組みを理解したうえで、将来に備えて計画を立てることで、受講のハードルがぐっと下がります。
判断に迷ったときは、「今やりたいこと」「1年後にできたらうれしいこと」を書き出してみると、意外と答えが見えてきます。
受講後に必要な登録変更や義務を事前に整理する
追加講習を受けると、それに伴って必要な登録変更や申請も発生します。
主な内容は以下の通りです。
- ライセンス記録の更新(LMSへの追加修了登録)
- 特定飛行の許可・承認申請(空撮案件ごとに必要)
- 機体の登録情報確認(安全機能・識別ライトの有無など)
また、追加講習を受けたからといって、どこでも飛ばせるわけではない点には注意が必要です。
自治体や施設の許可、近隣住民への説明など、マナーや地域ごとのルールもきちんと守る姿勢が大切です。



私は修了後、許可申請の手順に少し手間取りました。
でも一度経験すれば、次からはスムーズに準備できるようになります。
まとめ:ドローンの夜間飛行等の追加講習は将来の選択肢を広げる鍵
ここまで、目視外・夜間飛行のための追加講習について、制度や現場活用の実例を交えてお伝えしてきました。
一見ハードルが高く感じる追加講習ですが、その一歩を踏み出すことで、親子の空撮活動にも、仕事にも、確かな可能性が生まれます。
追加講習で得られる“許可”は自由な活動の土台になる
ドローンの飛行は「できる範囲」が明確に法律で定められており、無許可では違反になってしまう場面も多々あります。
しかし追加講習を受けて特定飛行の許可を得れば、その制限が一つずつ解放され、自由な活動の“土台”が手に入るのです。
それは「高額案件を受けられる」という経済的メリットだけでなく、「やってみたいを、実際にできる」状態を作り出すことに他なりません。
制度を知り、必要な訓練を受けることは、結果として“安心して飛ばせる楽しさ”につながっていくのです。



私自身、講習を受けたことで「いつでも、どこでも飛ばせる」という心の余裕が生まれました。
子どもと目指す空撮旅行にも応用できるスキル
そして何より、このスキルは“家庭内ライセンス”として大きな力を持ちます。
たとえば、子どもが「夜景を撮ってみたい」「キャンプ場で上空から家族を撮りたい」と言ったとき、親が追加講習を受けていれば、それが現実になります。
16歳で子どもが操縦資格を取得すれば、親子で夜間の空撮旅に出かけることも夢ではありません。
親が先に学び、制度と安全の土台を作っておくことで、子どもは法的制限を超える前から実践経験を積むことができます。
それが、将来の挑戦や選択肢を増やす“親からのギフト”になるのです。
制度、講習、費用は一見複雑そうに見えるこれらの情報も、ひとつひとつ整理して取り組めば必ず身につきます。
だからこそ、この記事があなたの「最初の一歩」になれば嬉しいです。








