最近、親子でドローンを楽しむ方が増えてきましたが、「公園や河川敷で飛ばしてもいいの?」と悩んでいませんか?
一見ひらけた場所でも、実はさまざまなルールや許可が必要になるケースがあります。
知らずに飛ばすと、最悪の場合は注意を受けたり、罰則の対象になることも。
実際、私自身もはじめて飛ばそうとした日、公園管理者から一言「ここは許可が必要なんですよ」と制止されてしまいました。
ですが、その経験が「どうすれば親子で安全に合法的に飛ばせるのか?」という学びの出発点になったのです。
この記事では、
- 公園や河川敷でドローンを飛ばす際に必要な許可の背景
- 申請手続きの具体的な流れと注意点
- 親子で気をつけたいマナーや現地ルールの実例
- 許可を得やすくする交渉のコツや体験談
などについて、元小学校教員の立場から丁寧に解説していきます。
あなたが安心して親子で空を楽しめるように、ぜひ最後までお読みください。
公園や河川敷でドローンを飛ばすにはなぜ許可が必要か?
「空を飛ばすんだから航空法だけ守ればいいのでは?」と考えがちですが、公園や河川敷では別の視点からの管理が行われています。
実は、ドローンの飛行には空のルールと地上のルール、2つの視点が必要なのです。
ここでは、公園や河川敷でドローンを飛ばす際に「なぜ許可が必要なのか?」を3つの観点から詳しく見ていきます。
航空法とは異なる地上の管理ルールとは
航空法は「どこまでの高さで、どういった安全基準で飛ばすか」を定めた国のルールです。
一方、公園や河川敷といった公共施設は、自治体や国交省などが管理する“地上空間”であり、そこには独自の使用ルールがあります。
たとえば、芝生保護のため機械の使用を制限していたり、イベントやスポーツ利用と重ならないよう飛行禁止の時間帯が設けられていたりします。

私も最初は「空を飛ばすだけなら大丈夫」と思い込んでいたのですが、管理事務所に確認したところ「地上施設内の使用行為」として申請が必要だと言われ、目から鱗でした。
つまり、飛ばす場所が私有地か公共地か、誰がその地面を管轄しているかを知ることが、スタートラインになるのです。
場所ごとの管理ルールだけでなく、屋外全体での法律もしっかり把握しておくと安心です。
飛行ルールの基礎を知りたい方はこちらも参考にしてください。


公園と河川敷で異なる許可の取り扱い実態
意外と知られていませんが、公園と河川敷では「許可の取り方」や「判断基準」が異なります。
公園は市区町村が管理していることが多く、窓口は都市公園課や地域振興課。
一方、河川敷は国交省や地方整備局、場合によっては土地改良区や土地所有者が管理しており、確認先がやや複雑になります。
公園と河川敷の許可窓口の違い
| 場所 | 主な管理者 |
|---|---|
| 市営・区営公園 | 市役所の公園管理課・都市整備課 |
| 国営公園 | 国土交通省・都市公園管理センター |
| 河川敷(大規模) | 国交省の地方整備局 |
| 河川敷(小規模) | 市町村・土地改良区など |
窓口が異なることで、許可が下りるまでのスピードや必要書類の種類も変わります。
「前に公園では簡単に飛ばせたのに、今回はなぜか断られた」というケースの多くは、この違いに起因しています。
私が最初に断られた理由と学び
私が初めてドローンを飛ばそうとしたのは、市内の大きな河川敷公園でした。
事前に航空法の勉強はしていたものの、「公園で飛ばすのに申請がいる」とは思っていなかったのです。
いざ現地でフライト準備をしていると、通りかかった管理スタッフに「すみません、ここは許可が必要なんです」と声をかけられました。
私はその場でフライトを断念し、帰宅後すぐに市のホームページと都市公園条例を調べました。



調べていく中で、「ああ、飛ばすだけでも“施設使用”になるんだ」と気づいたとき、自分の認識が甘かったと反省しました。
この経験から得た最大の学びは、「飛ばす前に“管理者の立場”で考えてみる」ことの大切さです。
今では、初めて行く場所では必ず1週間前に電話確認を入れています。
ドローン飛行許可を取得するための申請準備と手順
では実際に、公園や河川敷でドローンを飛ばす許可を取るにはどうすればいいのでしょうか?
「なんだか面倒そう…」と感じるかもしれませんが、手順を知っておけば驚くほどスムーズに進みます。
この章では、初心者の方でも迷わないように、窓口の探し方から書類の整え方、申請後の流れまでを具体的に解説します。
公園・河川敷ごとの申請窓口と確認方法
まず最初にやるべきことは、「どこがその場所を管理しているか」を調べることです。
公園の名前や住所をGoogleで検索し、公式サイトや市区町村の施設案内ページを開いてください。
“施設利用に関するお問い合わせ”や“都市公園条例”と書かれたページにたどり着ければ、そこが窓口です。
- 市役所・区役所のホームページで施設名を検索
- 「〇〇公園 使用許可」「〇〇河川敷 ドローン」と検索
- 地元の防災・土木・建設・観光課が関係する場合もある
- 窓口がわからないときは“公園名+市役所代表番号”に電話で確認
管理者が複数存在する場合は、「公園は市、河川敷は国交省」など、分担されていることもあります。
どちらに申請すべきか迷ったら、まずは“上位の管理者”に聞くと丁寧に教えてもらえることが多いです。
初心者向けに書類を整える3ステップ
書類を整えるには3つのステップがあります。
ひとつずつ順を追って確認すれば、初めてでも問題ありません。
- 1. 飛行目的を明確にする(例:親子での空撮練習、安全講習、課題研究など)
- 2. 使用希望日時とエリアを指定する(地図や写真を添付すると効果的)
- 3. 使用申請書・同意書などのフォーマットを取得し、記入・提出する



私ははじめ、用途の説明を「趣味の練習」とだけ書いて出したところNGでしたが、「16歳未満の子どもが航空法の許可外で安全に経験を積むため」と書いたところ、すんなり通りました。
相手に“なぜその場所で飛ばす必要があるのか”が伝わることが、審査のカギになります。
申請から許可が出るまでの目安日数と注意点
申請を出してから許可が下りるまでの期間は、おおよそ3〜10営業日が目安です。
しかし、イベントが重なる時期や申請内容に不備があると、さらに日数がかかることも。
特に「初回申請」や「繁忙期(春・秋の連休)」は早めの提出が鉄則です。
- 希望日の2週間前には申請を出しておく
- 申請書のフォーマットは最新版を使う
- 電話やメールでやり取りを記録に残しておく
- ドローンの機体情報(製品名・重量・飛行時間など)は必須記載
また、申請時に管理者から「見学したいので飛行日は教えてください」と言われることもあります。
その場合は、フライト時のスケジュールや人数などを事前に伝えておくと印象が良くなります。
ドローン飛行許可を取ったあとに守るべき現地ルールとマナー
許可をもらえたからといって、すぐに自由に飛ばしていいわけではありません。
現地には、利用者どうしの安全や快適さを守るためのルールやマナーが存在します。
この章では、私が実際に現場で経験した具体例を交えながら、飛行当日に気をつけるべきポイントをご紹介します。
飛行時間と利用エリアの具体的な制限
飛行が許可されたとしても、「いつでもどこでもOK」ではありません。
多くの公園や河川敷では、飛行可能な時間帯(例:9時〜17時)や、エリアの制限が設けられています。
これは、他の利用者とのトラブルを防ぐための大切な配慮です。
- 芝生エリアは立ち入り禁止(保護中)
- 混雑日(土日・祝日)は飛行禁止
- ペット散歩コース付近での飛行不可
- イベント開催日や近隣学校の行事と重なる日は要注意
こうした条件は、許可書に明記されていることもありますが、実際の現地環境は日によって異なるため、当日の状況判断も欠かせません。



私は過去に「許可書にはOKと書いてある」と思って飛ばそうとしたら、当日が地元の小学校マラソン大会と重なっていて、結局中止にしたことがあります。
通行人への配慮で信頼を得る
ドローンを飛ばすと、やはり人の目を引きます。
不安そうな表情の通行人に気づいたら、こちらから挨拶や説明をするだけで安心感が生まれます。
「許可を取って飛ばしています」「安全距離を取ってますのでご安心ください」といった声かけは、信頼を得るための一歩です。
通行人と良好な関係を築くことは、次回以降の飛行のしやすさにもつながります。
また、子どもが一緒にいる場合は、親が責任者であることを明確に伝えると、周囲の理解が得やすくなります。
許可証提示のタイミングと携帯の仕方
現地で管理者や警備員に声をかけられた場合、スムーズに対応できるように、許可証は必ず印刷して持参しましょう。
スマホでの表示だけでは信頼度が下がることがあります。
クリアファイルに入れてすぐ取り出せるようにしておくと便利です。
- A4の許可証コピー(カラー印刷)
- 対象エリアの地図(申請時と同じもの)
- ドローン機体の飛行仕様・保険加入証明のコピー
そして、飛行の前にスタッフが近くにいたら、こちらから許可証を見せて挨拶しておくと印象が格段に良くなります。
信頼関係の第一歩は、説明責任を果たす姿勢にあります。
初心者でもスムーズにドローン飛行許可を得るための裏技と交渉術
申請の手順を知っていても、「なぜか通らない」「対応が冷たい」と感じることはありませんか?
実は、管理者とのやりとりの中にちょっとしたコツを入れるだけで、申請の通りやすさは大きく変わります。
この章では、私が実際に試行錯誤しながら得た「交渉の工夫」を紹介します。
電話やメールでの伝え方で印象を変えるコツ
まず、問い合わせの際は「ただ聞くだけ」にならないように意識しましょう。
おすすめは、最初の一言に“配慮の姿勢”を込めることです。
たとえば、「他の利用者の迷惑にならない範囲で安全に練習したいと思っていまして…」という言い回しは、好印象を与えます。
メールでは、申請理由を1〜2文で簡潔に書いたうえで、相手の負担を減らすような配慮が鍵になります。
たとえば「指定書式があればダウンロードさせていただきます」など、相手の動きを先読みするとスムーズです。



私の場合、同じ公園に2度目の申請を出す際、「前回大変お世話になりました。今回も同様の内容で申請させていただきます」と書いたところ、前回よりも返信が早くなりました。
過去の成功事例から見えた許可が下りやすい条件
私はこれまでに8箇所以上の公園・河川敷に申請を出しましたが、比較的スムーズに許可が出たケースには共通点がありました。
- 平日・午前中など混雑しにくい時間帯を希望する
- 飛行目的が「教育的・家族的」な内容である
- 飛行回数が1回限り、または短時間である
- 保険加入済であることを明記している
特に「子どもの教育のため」という目的は理解されやすく、単なる趣味よりも公共性が高いと判断されることが多いです。
私が実際に許可を得た際の申請文テンプレート
以下は、私が実際に送った申請文の一部です。
メールや申請フォームに貼り付ける際に活用できるよう、文面例としてご紹介します。
お世話になります。
松本市在住の山本と申します。
このたび、〇〇公園にて、小学四年生の息子とのドローン飛行練習を希望しております。
航空法の対象外機体(100g未満)を使用し、飛行は安全距離とマナーを遵守して実施いたします。
日時:〇月〇日(土)10:00〜11:30予定
目的:親子での空撮技術の学習・屋外での実地練習
必要な書類がございましたら、ご指示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
このように、相手に「リスクが低く、信頼できそう」と感じてもらえる書き方が効果的です。
ドローンの技術よりも、“人として信頼される申請者”であることの方が、許可取得では何倍も重要だと実感しています。
まとめ:公園や河川敷でドローンを飛ばすための心得
ドローンを安心して飛ばすには、ただ「飛ばしたい」と思うだけでは不十分です。
場所ごとのルールを理解し、適切な申請と現場でのマナーを守ることが、継続的な飛行環境を育てる第一歩です。
そして何より、親としてその姿勢を子どもに見せることが、学びの最大のチャンスになります。
許可取得から飛行当日までの7日間プラン
忙しい中でも動きやすいように、申請から飛行当日までの流れを7日間でまとめてみました。
7日間で進めるドローン飛行準備プラン
| 日数 | やること |
|---|---|
| 1日目 | 目的・日時を決めて場所の管理者を調べる |
| 2日目 | 申請窓口に電話・メールで問い合わせ |
| 3日目 | 申請書作成・必要書類の準備 |
| 4日目 | 申請書を提出し、内容の確認連絡 |
| 5日目 | 必要に応じて補足資料の送付 |
| 6日目 | 許可証の受け取り・フライト当日の準備 |
| 7日目 | 現地で飛行、許可証提示・マナー順守 |
この流れを一度経験しておけば、次回以降の申請は驚くほどスムーズになります。



私も最初は10日以上かかっていましたが、今では2回目以降なら4〜5日で完了しています。
子どもと一緒に安全意識を育てる実践例
ドローン学習は、ただの操作技術だけでなく、ルールや責任感を学ぶ教材として非常に有効です。
わが家では、飛行の前日に「どんな危険がありそう?」「どこに注意する?」という話し合いを必ず行います。
ホワイトボードを使って“危険予測シート”を一緒に書いたり、YouTubeで事故動画を一緒に見てリスクを学んだこともあります。
親が率先して学ぶ姿を見せることで、子どもも自然と“考えて飛ばす”ようになります。
日々のちょっとしたルールづくりが、親子で安心して続けるコツになります。
家庭内でできる工夫や約束事についてはこちらも参考にしてみてください。
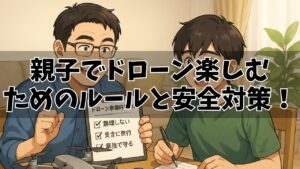
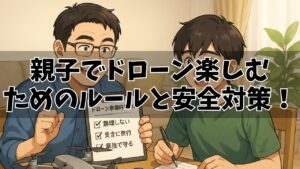
飛行後にトラブルを防ぐ報告・感謝の習慣
飛行が終わったあとも、ひと手間かけることで“次につながる信頼”が育ちます。
例えば、「本日はお世話になりました。安全に飛行できました。ありがとうございました。」という簡単なお礼のメールを送るだけでも印象は大きく変わります。
また、現地スタッフや通行人に「見せてくれてありがとう」と言われたときは、子どもにも「挨拶しようね」と伝えるようにしています。
親がマナーを大切にする姿を見せることで、「飛ばして終わり」ではなく「関係を築く体験」へと変わるのです。







