「親子でドローンって本当に楽しめるの?」そんな疑問を持つ方が増えています。
最近では、子どもの関心から始まったドローン体験が、家族の絆や学びの場へと広がっているケースが多く見られます。
特に、資格制度の整備や安全対策の充実により、親が先に学ぶことで子どもも安心してチャレンジできる環境が整いつつあります。
家族旅行、自由研究、レース体験、学校イベントの撮影、さらには農業体験まで。
ドローンはただの“おもちゃ”ではなく、親子の時間を彩る“未来のツール”として注目されています。
この記事では、
- 親子で実際に楽しめるドローン活用事例の紹介
- 年齢に応じた安全な学び方と家庭ルールの工夫
- 体験イベントや趣味としての可能性
- 家族全体に与える学習的・感情的な効果
などについて詳しく解説しています。
親子で広がるドローンの世界!実際に体験した活用事例5選
ドローンは親子の時間を豊かにする新しいツールとして、私たちの暮らしに少しずつ根づいてきました。
ここでは、実際に私たち家族が取り組んできた体験を中心に、ドローンを使ってどんな活動ができるのかを5つご紹介します。
楽しさの中にも安全性と学びが含まれており、それぞれが親子での対話や成長につながっています。
家族旅行での空撮:私たちの思い出を上空から記録
旅行先での景色やアクティビティを空撮すると、いつもの写真とはまったく違う記録が残せます。
例えば、長野県の山あいでのキャンプ場では、子どもたちがテントを張る様子を真上から撮影したことで、全体の動きがよく分かり、後で家族で動画を見返すのが恒例行事になりました。
スマホやビデオカメラでは撮れない「家族全体を包み込む視点」があることで、子どもたちも撮影に夢中になります。
気をつけたいのは、観光地や自然公園ではドローンの飛行制限がある場合もあることです。
事前に自治体や管理者に確認を取るのを忘れないようにしましょう。

山の中での空撮はGPSの受信状況に注意が必要でした。
旅行先での空撮に慣れてきたら、さらに高い視点からの撮影にも挑戦できます。
その際の飛行ルールや撮影のコツについてはこちらの記事を参考にしてください。


親子で作る自由研究:ドローンを使った観察・測定の工夫
自由研究のテーマとして、ドローンの飛行距離や風によるブレの影響を調べたことがあります。
飛行ルートを記録して、何メートル先まで安定して飛べるかを観察したり、日陰と日向で気温差がある場所で赤外線カメラを使って温度変化を比較するなど、科学的な探究にもつなげられました。
「何を観察するか?」「どんな手順で?」を親子で話し合いながら決めていく過程が、ただの実験以上に価値のある時間になります。
さらに、学校に提出する際には飛行時の安全ルールや操縦者の資格についても説明を加えると、先生からの評価も高くなります。



ドローンを「遊び道具」で終わらせず、学びに昇華させるには親の関与が不可欠だと感じました。
ミニレース:親子対決で盛り上がる週末の遊び
広場や体育館を使って、ドローンの障害物レースを親子で行ったことがあります。
フラフープをくぐらせる、小さな輪の中を通過させる、タイムトライアルをするなど、ルールを工夫することで競技性も出て、子どもたちは大興奮。
私自身は機械操作に自信がなかったのですが、練習していくうちに操作スキルが上がり、息子との勝負も互角になってきました。
勝敗よりも「操作に集中する時間」を共有することが大切だと感じました。
家の中ではスペースが限られるため、安全な屋外か体育館などを使うとより自由に遊べます。



「今日はパパに勝った!」と言われる瞬間が、実はいちばん嬉しかったりします。
イベント撮影:運動会や発表会を上空から撮る挑戦
学校のイベントでは、望遠レンズでは捉えきれない全体の動きをドローンで記録できます。
もちろん、事前の許可や撮影エリアの確認は必須ですが、学年全体の演技を上空から撮ることで、家族だけでなく他の保護者にも喜ばれました。
私たちは運動会のリハーサル日に、学校の先生方と相談してテスト飛行を行い、安全確認のうえ本番での撮影を行いました。
音が気になる機種では演技の妨げになる可能性もあるため、静音ドローンの選定が重要です。
また、撮影した映像を編集して保護者会で共有すると、交流の場にもなりました。
- 学校側の許可と保護者への事前通知
- 飛行エリアの安全性と生徒との距離
- 撮影機材の音量と飛行時間
こうした注意点を踏まえると、トラブルなく良い記録が残せます。
農業体験でドローンによる種まき
親戚の畑で行った農業体験では、ドローンによる種まきや液体肥料の散布に挑戦しました。
専用の農業用ドローンを使用し、安全対策を取ったうえで操作を体験させてもらいました。
子どもにとっては、自分の動きが作物の育成に直結するという実感が強かったようで、数週間後に芽が出た時はとても嬉しそうでした。
都市部ではなかなか体験できない内容ですが、農業体験プログラムなどで参加できる場所も増えています。
単に技術を学ぶだけでなく、「自然と人の関わり」を体で感じられる貴重な機会です。



命を育てるドローンの使い方に、私自身も深く感動しました。
子どもと一緒に始めるドローンの学び方と楽しみ方
ドローンを親子で安全かつ継続的に楽しむには、「いきなり屋外で飛ばす」前に家庭内で段階を踏んでいくことがとても重要です。
私たちの家庭でも、まずはトイドローンから始め、徐々に機体や操作内容をレベルアップさせていきました。
このプロセスが、子どもの興味を深めるだけでなく、家族全体の学びとしても豊かなものになります。
子どもでも扱えるトイドローンで最初の一歩
最初に選んだのは、手のひらサイズで屋内用のトイドローンでした。
重量が200g未満であるため航空法の適用対象外となり、免許や登録なしで飛ばせる点が魅力です。
ただし、安全を確保するためにも「親が横にいる状態」で操作するようにしています。
プロペラガード付きのモデルを選ぶことで、家具や壁を傷つけるリスクも減らせました。
家の中で「着陸場所にコップを使う」など、ゲーム感覚の練習メニューを作ると、子どももすぐに夢中になります。



最初は壁にぶつけてばかりでしたが、1週間もすれば安定してホバリングできるようになりました。
家庭内ルールと練習スケジュールの立て方(わが家の例)
家庭内での練習を続けていくためには、ルールとスケジュールの整備がカギになります。
わが家では「飛ばす前に10分間のシミュレーター練習を行う」「トイドローンはリビングのみで使用可能」など、具体的なルールを設定しました。
さらに、毎週土曜日の午後に1時間だけドローン時間を設け、親子で交代しながら飛行や動画撮影に取り組んでいます。
こうした予定をホワイトボードに書いておくことで、家族の中での「ドローンの時間」が自然に共有されるようになりました。
また、練習のあとに撮影した映像を見返すことも学びの一環としてとても効果的です。
- 場所・時間・順番を明確に決めておく
- 親子で交代しながら操作と見守りを担当する
- 練習後にふりかえりの時間を取り入れる
こうしたルールがあることで、子どももドローンを「特別な学びの道具」として扱うようになります。
親が資格を取ることで安全と自由が一気に広がる
トイドローンでの練習を積んだあと、私自身は「二等無人航空機操縦士」の資格取得に挑戦しました。
理由はシンプルで、「子どもがもっと本格的なドローンを使いたがったときに、安全に飛ばせる環境を整えたい」と思ったからです。
資格を取ることで、法令に準じた知識や飛行申請の手続き、補助者との連携方法などが身につき、家族全体で飛ばせる場所の幅が広がりました。
特に河川敷やイベントでの空撮を行う際は、「保護者である私が資格を持っている」という信頼が学校や地域との交渉でも役立ちました。
国家資格の取得は簡単ではありませんが、「親が先に挑戦する」姿は子どもにとって強いメッセージになります。
資格取得を考えるなら、講習の日程確保も重要な準備のひとつです。
予約が取りづらい理由や、スムーズに予定を押さえるコツについてはこちらの記事を参考にしてください。
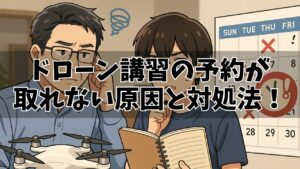
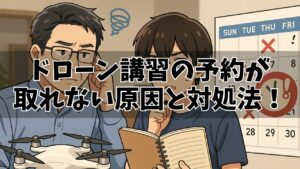



息子は「次は僕も取りたい」と言って、今はシミュレーターで練習を始めています。
親子で挑戦できるドローン体験活動の探し方と選び方
家庭内のドローン練習から一歩進んで、外部イベントに参加することで、より多様な経験を親子で共有することができます。
ただし、体験イベントには対象年齢やルールがあるため、事前の下調べと準備が欠かせません。
ここでは、実際に私たちが参加した体験イベントの情報や、参加時に役立ったチェックポイントをまとめました。
全国で開催されている親子向けドローン体験イベント
最近では、自治体や民間のスクールが主催する「親子ドローン体験教室」が全国各地で開催されています。
内容は初心者向けの操作体験から、プログラミング飛行、空撮ワークショップ、ミニレース大会まで多岐にわたります。
特におすすめなのが、地域の公民館や科学館で実施されている小規模イベントです。
1クラス10名以下で指導が丁寧なため、初めてでも安心して参加できます。
私たちが初めて参加したのは長野県塩尻市の市民活動センター主催のワークショップで、地元の指導員が飛行体験をサポートしてくれました。



少人数で親子ペアでの参加だったので、子どもが緊張せず楽しめたのが良かったです。
参加前に確認すべき対象年齢と保護者ルール
イベントによっては、参加可能な年齢が「小学生以上」「中学生以下は保護者同伴」など細かく定められています。
また、「保護者は補助者として必ずそばに立つこと」「操作は1人ずつ交代で行う」などのルールがある場合もあります。
これらのルールは安全のために設けられているため、事前にイベント案内ページでしっかり確認しましょう。
心配な場合は、主催者に直接問い合わせるのも安心につながります。
とくに高性能なドローンを使うイベントでは、技能認証や機体登録の有無を聞かれることもあります。
- 対象年齢と同伴ルールの有無
- 使用する機体の種類と飛行範囲
- 保険加入の有無や緊急時の対応体制
イベントが安全に進行するかどうかは、こうした確認の積み重ねで決まります。
体験後アンケート:実際に参加した家庭の声と学び
体験イベントの多くでは、終了後に簡単なアンケートやふりかえりの時間があります。
私たちも参加後に「楽しかったこと」「難しかったこと」「家でもやってみたいこと」を紙に書く機会がありました。
子どもの感想を見ると、親が想像していた以上に「操作して注目されること」や「うまく飛ばせた達成感」に価値を感じていることが分かりました。
また、他の親御さんたちと話す中で「やっぱり親が先に資格を取ってから子どもに勧めたい」「家ではルールがあった方がよさそう」など、共通の悩みや気づきを共有できたことも大きな収穫です。



「次はどこに行こうか?」と話し合うのも、もうイベントの一部なんですよね。
ドローンを使った趣味の可能性と家族の時間の作り方
ドローンをきっかけに、家族の時間が変わった──そう感じる瞬間が、私たちの家庭では何度もありました。
単なる遊び道具にとどまらず、編集や設計などの周辺スキルに発展させることで、趣味の幅がぐっと広がります。
また、家族の会話が変化し、親の学び直しにもつながるなど、ドローンには多面的な魅力があると感じています。
趣味としてのドローン:映像編集・飛行ルート設計など
ドローン飛行を楽しむだけでなく、撮影した映像を編集する時間が親子の新しい趣味になりました。
無料の動画編集ソフトを使って、音楽をつけたり、テロップを入れたりすることで、作品としての完成度も上がります。
また、事前に飛行ルートを紙に描いてみる「フライト設計」も、意外と頭を使う楽しい作業です。
地図アプリを使って飛行予定ルートを確認し、「この角度から山を映したい」「このタイミングで旋回しよう」など、まるで映画監督のようなやり取りになります。



「その音楽いいね」「その編集面白いね」と親子でアイデアを出し合う時間は、何よりの宝物です。
家族の会話が変わる!共通のプロジェクトで学ぶ週末
ドローンという共通の関心ごとができたことで、週末の家族の会話がガラリと変わりました。
以前はテレビを見たり、それぞれがスマホを触って過ごしていた時間が、「次はどこで飛ばす?」「この前の映像どうだった?」という建設的な話題に変わったのです。
「パパは前より慎重に飛ばすようになったね」「僕も次は水平に保ちたい」など、お互いの成長を認め合う会話が自然と生まれます。
何より、ドローンを通じて“同じ目線で話せる時間”が増えたことが、家族のつながりを強くしたように感じます。
共通プロジェクトがあるだけで、家庭はぐっと活気づきます。
- 目標を小さく分けて週単位で設定する
- 役割分担(操縦、撮影、編集など)を明確にする
- 完成品を誰かに見せる場を設ける
こうすることで、日常がちょっとした冒険に変わります。
親のリスキリングにもなる!技術習得のメリット
ドローンに関わることで、私自身がこれまで触れてこなかった技術に向き合うようになりました。
例えば、気象情報の読み取り、電波干渉の知識、映像編集ソフトの使い方など。
最初は「難しそう…」と思っていた分野も、実際に使う場面があると不思議と覚えられるものです。
この経験は本業とは別の副業チャンスや講師依頼にもつながり、まさにリスキリングそのものでした。
そして、子どもから「パパも勉強してるんだね」と言われると、学び続けること自体が親の背中として伝わっているのだと実感します。



40代半ばで“まさか自分が資格を取るなんて”と思っていましたが、それが家族にとって一番の変化だった気がします。
まとめ:ドローンは親子で未来を描ける最高の学び道具
ここまで紹介してきたように、ドローンは「遊び」や「趣味」を超えて、親子の時間そのものを豊かにしてくれるツールです。
飛ばすことを目的にするのではなく、そこから生まれる会話・観察・学びの積み重ねが、子どもたちの未来を形づくっていきます。
そして何より、親がその一歩を踏み出すことで、家庭内に「挑戦する文化」が育っていきます。
最初の一歩は家庭内での「安全+遊び」から
高価な機材や資格取得をいきなり目指さなくても、まずはトイドローンから始めることで十分です。
家の中でのホバリング、着陸場所へのチャレンジ、簡単な動画の撮影。
どれも子どもにとってはワクワクする「冒険」の連続です。
そして、安全に遊ぶルールを親子で決めて実行していくことが、ドローンを「道具」として活かす第一歩になります。



遊びながらルールを守る経験は、どんな教材よりも深く身につきます。
「夢中」が「未来のスキル」になる時代の親の役割
子どもがドローンに夢中になることに、不安を感じる親御さんも多いかもしれません。
ですが、その「夢中」は放っておくとすぐに消えてしまうものでもあります。
だからこそ、親がその好奇心に伴走し、「資格」「知識」「振り返り」という“土台”を用意してあげることが大切です。
たとえば「なぜ電波が届かなくなるのか」「どうして屋外では申請が必要なのか」といった問いに、親が一緒に答えを探していくことで、子どもは“学ぶ楽しさ”を知っていきます。
- まず親が情報を集めて安全を整える
- 一緒にルールや練習計画を作成する
- 「わからない」をそのままにせず一緒に調べる
ドローンは、親子で未来を設計するきっかけになります。
あなたが今日、子どもと一緒に空を見上げることで、その未来はすでに始まっているのかもしれません。








