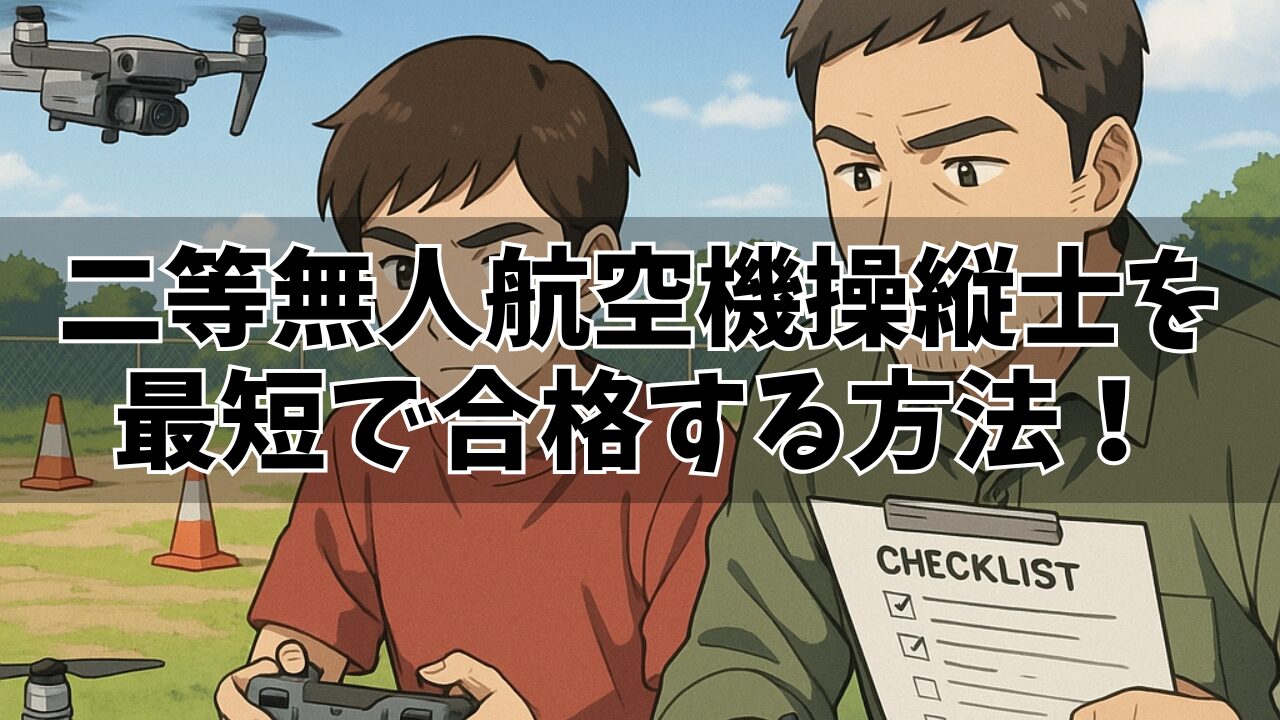二等無人航空機操縦士という国家資格をご存知でしょうか?
実はこの資格、16歳から取得できる上に、将来的なドローン活用に向けた重要なステップとして注目を集めています。
特に最近では、「子どもがドローンをやりたがっているけど、どうすれば安全に飛ばせるの?」という親御さんからの相談が増えてきました。
資格制度や機体の選び方、安全対策など、疑問を抱えながらも第一歩を踏み出せずにいる方が多いのが現状です。
そんな中、国の制度が整い、ドローンの国家資格取得がより身近になったことで、「家族で学ぶドローンライフ」を始める家庭も増えてきました。
親が先に学ぶことで、子どもも年齢制限前から安全に体験する第一歩として、この記事をご覧いただけたらと思います。
この記事では、
- 二等無人航空機操縦士が注目される背景と制度の概要
- 試験内容・合格基準・必要な準備のすべて
- 親子で学ぶときのスケジュールや導入ステップ
などについて詳しく解説しています。
二等無人航空機操縦士とは?16歳から取れるドローン国家資格の入口
ドローンを安全に飛ばすための国家資格として、「無人航空機操縦士」が創設されたのは2022年12月。
その中でも、16歳以上で取得できるのが「二等無人航空機操縦士」です。
これは「目視内飛行」や「第三者の上空を飛ばさない」などの条件を前提に、ドローンをより安全かつ自由に操縦するための正式なライセンスとなります。
家庭での空撮や子どもの練習といった用途にも適しており、まさに「親子でドローンを学ぶ」ための最初の一歩にぴったりな資格です。
ここでは、国家資格としての二等無人航空機操縦士について、その位置づけと取得の全体像を解説していきます。
国家資格の種類と違いを比較:一等と二等の選び方
ドローンの国家資格には「一等」と「二等」の2種類があります。
大まかな違いは飛ばせる範囲と操作の難易度にあります。
| 資格の種類 | 主な用途・飛行範囲 |
|---|---|
| 一等 | 有人地帯(第三者上空)を飛行する必要がある業務向け(例:物流、災害調査) |
| 二等 | 目視内で、第三者の上空を避けた飛行が前提。個人の空撮や業務入門に適する |
親子での空撮や学校行事の記録といった活動には、「二等」資格で十分対応できます。
費用や受講時間も比較的コンパクトなため、まずはここからスタートするのがおすすめです。

私も最初は「一等のほうが上級っぽいから」と悩みましたが、家族や地域イベントでの使用には「二等」で十分だと実感しています。
二等無人航空機操縦士の受験資格と16歳の条件
この資格の大きな魅力は、16歳から取得可能という点です。
法律上、年齢以外には「身体的・精神的に操縦に支障がないこと」だけが明記されており、特別な前提知識や学歴は不要です。
これは、ドローンが「誰にでも開かれた技術」になってきた証でもあります。
保護者がまず資格を取得し、飛行責任者となることで、16歳未満の子どもも同伴で安全に体験できます。
たとえば、小学生の子が操縦を体験する場合でも、保護者が「技能証明者」として同行すれば実践が可能になるのです。
このように、「親が先に資格を取り、子どもに安全な機会を与える」という流れが、家庭でのドローン学習において非常に効果的です。
受講先の探し方:登録講習機関の見極めポイント3つ
資格を取得するには、「登録講習機関(RePL機関)」での受講が必要です。
全国に複数の講習機関がありますが、以下の3つのポイントを基準に選ぶと安心です。
- 通いやすい場所にあるか(自宅からの距離、交通手段)
- 受講者のサポートが充実しているか(事前資料、模擬問題の提供など)
- 費用体系が明確であるか(追加費用の有無、分割払いの可否)
特に親子で学ぶ場合、同時受講割引や個別指導の対応可否も確認しておくと安心です。



私が通ったスクールでは「親子同時割引」がありました。説明も丁寧で、最初のメールから好印象だったのが決め手でした。
資格取得の第一歩は、安心して相談できる講習機関を選ぶところから始まります。
ドローン国家資格の試験内容と合格基準を完全解説
資格を取るうえで気になるのが「どんな試験があるのか?」「どのくらい難しいのか?」という点です。
二等無人航空機操縦士の試験は、大きく分けて「学科試験」と「実地試験」の2つで構成されています。
それぞれに合格基準が定められており、登録講習機関での講習を経て受験することが一般的です。
ここでは、合格に向けて知っておきたい試験の中身と、合格ラインを詳しく解説していきます。
学科試験の出題範囲と合格ラインの目安
学科試験では、ドローンの安全飛行に関わる知識が問われます。
主な出題範囲は以下の通りです。
- 航空法や電波法などの法令
- ドローンの構造・運用・電源に関する知識
- 気象や飛行環境についての基本的理解
問題形式は多肢選択式で、講習修了者であれば実際の試験は比較的やさしいと感じる人も多いです。
合格ラインは、各科目ごとに正答率70%以上が目安とされています。
学科は「理解よりも記憶」が問われる面が強いため、過去問演習と模擬試験が最短ルートになります。
オンラインで無料配布されている模試も活用しましょう。
なお、講習機関によっては学科試験を免除するケースもあります(国の規定による講習修了者の場合)。



私は最初「航空法なんて覚えられるかな」と不安でしたが、模試を繰り返すことで自然と頭に入り、試験当日には8割以上取れました。
実地試験の流れと操縦評価ポイント一覧
実地試験では、ドローンを実際に操作する技術と判断力が評価されます。
評価されるのは以下のような項目です。
| 評価ポイント | 内容の例 |
|---|---|
| 点検・安全確認 | 離陸前のチェック、周囲確認、電波状況の確認など |
| 基本操作 | 離陸、ホバリング、前後・左右の移動、旋回 |
| 緊急時の対応 | 障害物回避、異常時の判断、フェイルセーフ操作 |
この試験では、GPSあり・なしの両方で飛行操作を行うため、感覚任せの操作ではなく、「安定性」と「安全確認の習慣」が評価されます。
また、試験中は講師が常に評価シートをもとにチェックしており、「操作精度」「声出し確認」「周囲への配慮」も減点対象になることがあります。



最初の練習で「ホバリング5秒」をクリアできず焦りましたが、足場の目印を使ったことで安定するようになりました。
操作自体に慣れてきても、思わぬミスで減点されることがあります。
模擬試験の活用法:実力チェックと弱点補強のコツ
模擬試験は、自分の理解度と実力を測るうえで非常に有効な手段です。
特に独学の場合、「つもり理解」ではなく「実際に点が取れるか」をチェックする役割があります。
以下のようなステップで模試を活用するのがおすすめです。
- まずは1回分を通して解き、時間配分と形式に慣れる
- 不正解の問題だけをピックアップして復習
- 3日後に再度同じ模試をやり、定着度を確認
古い試験制度に基づいた模試も多く出回っているため、最新の出題傾向に対応した模試を選びましょう。
講習機関の公式教材に含まれている場合は、それを優先して使うのが確実です。
模試を繰り返す中で、自分の苦手なパターンや科目の癖が見えてきます。
その情報を使って学習スケジュールを微調整することで、合格にぐっと近づくことができます。
以下の記事を読んで、本番前に「どこで点を落としやすいのか」を把握しておくだけでも、大きな安心感につながりますよ。


二等操縦士を最短で合格するためのドローン試験勉強法とスケジュール設計
資格を取ろうと決めたものの、「仕事や家事がある中で勉強時間がとれるか不安」という方も多いと思います。
実際、最短合格のカギは“毎日の小さな積み重ね”です。
ここでは、私自身が取り組んだ勉強スケジュールと教材活用のコツをベースに、無理なく合格を目指せる勉強法をご紹介します。
私が実践した1日30分×60日の合格プラン
まず私が最初に意識したのは、「毎日30分だけやる」という時間管理の工夫です。
机に向かうのではなく、スキマ時間にスマホで動画を観たり、移動中に用語を復習したりと、“生活に組み込む”ことを意識しました。
以下は実際のスケジュールの一例です。
| 期間 | 取り組んだ内容 |
|---|---|
| 1〜15日目 | 学科講義の視聴+ノートまとめ(1回転) |
| 16〜30日目 | 模試+用語カード+過去問(1日1セット) |
| 31〜45日目 | 実技動画でイメトレ、操作練習(室内ホバリング) |
| 46〜60日目 | 模試復習+実技教本で安全点検手順の暗記 |
「毎日やることが明確」だと、習慣化しやすくなり、継続への心理的ハードルが下がります。



最初の10日間は疲れて寝落ちすることもありましたが、朝の10分に切り替えたら継続できるようになりました。
独学でも安心な参考書・問題集・動画教材リスト
講習前にある程度学んでおくと、講義内容が頭に入りやすくなります。
市販の教材でも、初心者向けに分かりやすく作られたものが増えてきました。
- 『ドローン国家資格 二等操縦士 試験対策テキスト』:法令も丁寧に解説されていて初心者向け
- 『2025年度版 二等操縦士 模擬問題集』:最新傾向を反映。試験慣れに最適
- YouTube「空撮ちゃんねる」:無料で視覚的に学べる実技動画が豊富
複数の教材を同時に使わず、1冊を繰り返すことが最短合格の鉄則です。
動画教材は、実技イメージや操作手順を“見て覚える”のにぴったりです。



教員時代のクセで教材を選びすぎたのですが、結果的に「1冊の反復」が一番効果がありました。
オンライン講座と通学講習の併用メリットと選び方
今はオンライン講座だけでもかなり学べる時代ですが、通学講習との併用は大きな強みになります。
以下は併用するメリットと、選び方の基準です。
| 併用のメリット | 理由 |
|---|---|
| 理解の定着 | 動画でインプット、対面でアウトプットすることで知識が深まる |
| 不明点をその場で質問 | 教官にすぐ聞ける環境が不安解消に役立つ |
| 試験本番の雰囲気に慣れる | 模擬試験や実地練習で自信がつく |
費用を抑えつつ併用したい場合は、「講義だけオンライン+実技だけ通学」がおすすめです。
講習機関によってはセット割引がある場合もあるので、事前に問い合わせるとよいでしょう。



私は「学科講義:動画」「実技:現地講習」で申し込みましたが、それぞれの特性を活かせて効率的でした。
ドローン免許の取得期間と手続きの流れを事前に把握しよう
「合格したらすぐに飛ばせるの?」と思われるかもしれませんが、実は試験合格のあとにもいくつかの重要な手続きが必要です。
ここでは、申し込みから資格取得、そして飛行までの流れを具体的に解説します。
申し込みから合格までのタイムラインと注意点
ドローン資格は、講習機関への申込から試験合格、証明書の交付申請まで段階的に進みます。
以下は一般的なスケジュールの目安です。
| ステップ | 目安期間 |
|---|---|
| 講習機関に申し込み | 1週間 |
| 学科・実技講習 (講習機関による) | 1〜2週間 |
| 修了試験の合格 | 講習最終日または翌週 |
| 国への技能証明申請 | 1〜2週間 |
| 証明書発行・届くまで | 約2週間 |
すべてがスムーズに進んでも、トータルで1ヶ月〜1.5ヶ月程度を見ておくのが安全です。



私は試験合格後、申請でつまずきました。マイナンバーカードが読み取れず、対応機器を買う羽目に…。早めの準備が肝心です。
受験・講習にかかる費用と節約テクニック
資格取得には一定の費用がかかります。
平均的な金額の目安は以下の通りです。
- 登録講習費用:15万円〜25万円(機関による)
- 証明申請手数料:3,000円前後
- 写真撮影・書類準備などの実費:1,000〜2,000円
家計の負担を抑えたい場合は、以下のような工夫も有効です。
- 早割・紹介割・親子同時申込の割引制度を活用する
- オンライン講座を事前に受けて、通学日数を最小限に
- 自治体の助成金制度があるか調べる(特に地域振興や就労支援)
とくに親子での受講を検討している場合は、講習機関に直接相談すると柔軟に対応してもらえることもあります。



うちは夫婦で交互に通えるように相談した結果、柔軟な日程と割引を提案してくれました。思い切って聞いてみるのが正解でした。
合格後に必要な登録・申請とその手順
試験に合格して終わりではありません。
正式に「技能証明書」を受け取るには、国への登録手続きが必要です。
手続きには以下のような流れがあります。
- 民間講習機関から修了証明書を受け取る
- 国土交通省の「技能証明ポータル」からWeb申請
- マイナンバーカードによる本人認証(ICカードリーダーが必要)
- 審査通過後、証明書が郵送で届く
「技能証明書」が届いて初めて、法的に飛行が許可されることになります。
そのため、申請書類の不備や認証トラブルは、飛行開始時期の遅れに直結します。
- マイナンバーカードとICカードリーダー
- 顔写真(規定サイズで撮影)
- 本人確認用のメールアドレス・電話番号
- 講習機関からの修了証PDF
準備が整っていれば、登録自体は20分ほどで完了します。
事前のチェックリストと早めの書類整理が、最後の安心につながります。
まとめ:16歳で国家資格を取りドローンの世界を家族で飛び出そう
ドローンの国家資格は、もはや一部の専門職だけのものではありません。
16歳から取得できる「二等無人航空機操縦士」は、家庭でも活用できる身近なスキルとして、多くの可能性を秘めています。
特に、親が先に学び、子どもの挑戦をサポートする姿勢は、家族全体の成長につながります。
最後に、「今すぐできる導入ステップ」と「親が先導する学び方」のコツをまとめてお伝えします。
今から始められる3ステップ(親子での導入編)
ドローンの資格取得までの道のりは長いようで、実は小さな一歩の積み重ねです。
以下は、今夜から始められる導入ステップです。
- トイドローンを調べて、購入候補を3つに絞る
- 無料シミュレータアプリをインストールして試す
- 家族ミーティングで「いつ・誰が・どう学ぶか」を話し合う
資格の話をいきなり持ち出すのではなく、「遊びながら試す→楽しさを共有する」流れでスタートすると、家族全員が前向きになります。



うちはまず長男が興味を持ったきっかけを全員で話し合い、「じゃあお父さんが先に資格取ってみようか」と自然な流れで始まりました。
「本当に家族で楽しめるの?」と不安な方もいるかもしれません。
でも実際には、親子で取り組める体験の選択肢は意外と豊富にあるんです。
安全と自由を両立する“親が先導する学び方”
ドローンは空を飛ぶ道具である以上、自由さと同時に責任が伴います。
そのバランスを取るためには、安全という土台を親が先に築くことが重要です。
資格取得の過程そのものが、子どもにとって最高の教材になります。
失敗や迷い、再挑戦の背中を見せることで、子どもも「挑戦は年齢じゃない」と感じてくれるはずです。
「空撮」や「国家資格」という言葉に構える必要はありません。
大切なのは、親が“できること”から始め、“できる姿”を見せること。
それが、家族で空を飛ぶための第一歩になるのです。



合格証が届いた日、壁に貼った瞬間に息子が「次は僕が取る番だね」と言いました。親子で1枚ずつ、並べられるその日が楽しみです。
いきなり本番機を操作するのは不安という方には、ミニドローンを使った安全な練習方法があります。
こちらの記事を読むと、親子で楽しくステップアップする方法がわかりますよ。