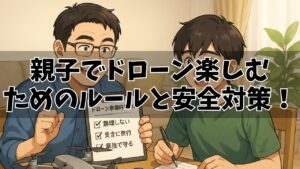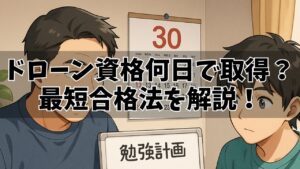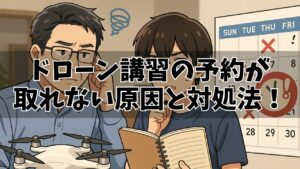「親子でドローンを飛ばして旅行先の思い出を空から残したい」
そんな夢を描く方が増える一方で、「法律や許可がわかりにくい」「何から準備すればいいのか見えない」と感じていませんか?
実は、ドローンを使った空撮旅行にはいくつかの重要なステップがあり、それを知らずに出発するとトラブルになる可能性もあるのです。
特にお子さんと一緒に飛ばす場合は、年齢制限や親の責任など、押さえるべきポイントが複数存在します。
この記事では、親が先にドローン資格を取得し、家族全体で安全に楽しむ空撮旅行のモデルケースを紹介します。
- 親子で始めるドローン旅行の魅力と計画の立て方
- 出発前に確認すべき法律と飛行許可の申請方法
- 親子ダブルライセンスによる国家資格の取得ステップ
- 空撮旅行に必要な機材・予算とスケジュール管理法
などについて、実体験をもとに詳しく解説していきます。
親子で始めるドローン空撮旅行のはじめ方ガイド
子どもと一緒にドローンを飛ばす時間は、単なる遊びを超えて“家族で共有する冒険”になります。
その楽しさを最大化するのが「空撮旅行」という新しいスタイルです。
家族で訪れた場所を、空から記録できるは、日常では味わえない視点と思い出を作るきっかけになります。
家族の趣味としてのドローン活用と空撮旅行の魅力
我が家では、長男が「運動会を上から撮れたら面白そう」と言い出したのがきっかけでした。
それを聞いて、私は“空からの視点”という発想にわくわくし、中古のトイドローンを買って試してみたのです。
はじめはリビングで植木鉢を倒すハプニングもありましたが、それがきっかけで「親が先に資格を取って、安全に遊ぼう」という家庭内ルールが生まれました。

「ドローン=危ないおもちゃ」と思っていた妻が、映像を見て「こんなにキレイなの!?」と驚いた瞬間、家族の意識が一変しました。
空撮旅行の魅力は、景色を残せるだけではありません。
計画・準備・飛行・振り返りという一連のプロセスを通して、親子で「一緒に挑戦する」こと自体が大きな価値になります。
- 視点の拡張:地上からでは見えない風景が「家族の記録」として残せる
- 共同作業:飛行の準備・操作・撮影後の確認まで、親子で役割を分担できる
- 感動の共有:旅先で撮れた映像を帰宅後に編集して、家族全員で見返せる
こうしたプロセスが、親子の会話や学びのきっかけになりやすく、旅行自体の価値を深めてくれます。
初心者でも実践できるドローン旅行計画の全体像
ドローン旅行と聞くと、「機材が難しそう」「許可が複雑そう」と身構えるかもしれません。
ですが、実は大まかに4つのステップに分けることで、親子でも着実に進められます。
| ステップ | やることの概要 |
|---|---|
| ①学ぶ | 親が法律・機材・飛行ルールを把握し、必要に応じて資格取得 |
| ②選ぶ | 旅行先や撮影スポット、使うドローンの選定 |
| ③申請する | DIPSなどで飛行許可を取得(必要な場合) |
| ④飛ばす | 現地での撮影+安全対策+思い出を記録 |



最初に一度だけ「親が下調べと制度整理」をしておけば、2回目からは家族行事として自然に組み込めるようになりました。
もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。
重要なのは、親が一歩踏み出して「安全の仕組み」を子どもに見せること。
そうすれば、子どもも自然と「準備して飛ばす楽しさ」を学んでいきます。
旅行前に確認すべき法律とドローン飛行許可の手順
ドローンを旅行先で飛ばすには、単にバッテリーを充電するだけでは不十分です。
航空法や自治体のルール、飛行許可の申請など、見落とすと“飛ばせない”事態に陥る可能性もあります。
特に親子旅行では、「子どもが飛ばしたいタイミングで飛ばせる環境」をつくるには、事前準備がカギになります。
空撮旅行で必要な飛行許可と飛行禁止区域のルール
まず、航空法に基づき、下記の条件に該当する飛行は国土交通省の許可または承認が必要です。
- 人口密集地(DID地区)での飛行
- 夜間飛行や目視外飛行
- 人や建物から30m未満での飛行
旅行先の観光地や公園がDID地区に該当するケースは多く、「その場で飛ばせない」ことも珍しくありません。
- 航空法の対象エリア:DID地区や空港周辺
- 自治体の条例:都市公園条例など、ドローン禁止の場合あり
- 施設独自のルール:観光地や宿泊施設での飛行可否
旅行の数週間前には、これらを地図と照らし合わせながらチェックしておくのが安心です。



一度、湖の上で飛ばそうとしたら「県の自然保護条例」でNGだったことがあります。飛ばす前に電話一本、忘れずに。
特に公園や河川敷での飛行を考えている方は、別途必要な申請や注意点も把握しておきましょう。
詳細な手続きの流れはこちらで確認できます。


DIPS2.0による飛行許可申請と旅先での注意点
国土交通省の「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」は、ネット上で飛行許可申請ができる便利な仕組みです。
ただし、申請から許可が下りるまでには最低10日〜2週間程度かかるため、旅行が決まった時点で準備を始めるのが理想です。
DIPS2.0では以下のような情報を入力します。
- 飛行エリアの地図
- 飛行目的とルート
- 使用する機体の情報
実際に飛ばす際には、申請内容とズレが出ないよう、現地での状況確認と第三者の安全確保も徹底しましょう。
未成年が飛ばすときの親の責任と同行者の役割
ドローンは「操縦できれば誰でも飛ばしていい」わけではありません。
16歳未満が操縦する場合、必ず保護者や指導者の監督が必要です。
また、飛行中の事故やトラブルが発生した場合は、保護者が法的責任を問われる可能性もあります。
そのため、旅先でお子さんが飛ばす場合でも、親自身が機体の性能や法的制限を理解したうえで、常に同行・補助することが前提です。



「子どもに任せればOK」と思っていた時期もありましたが、ルールを知れば知るほど「親が学ばないと守れない」ことに気づきました。
これから親子でドローン旅行を考えるなら、まずは親が制度の“通訳”になれるよう、法律と申請手順を押さえておくと安心です。
親子で国家資格を取ってドローンを楽しむ方法
「旅行だけなら資格はいらないんじゃないの?」
そう思われる方も多いかもしれませんが、実はドローンの国家資格は、親子でドローンを安全かつ自由に楽しむための“鍵”になります。
特に将来、目視外飛行や夜間撮影にも挑戦したいと思っているなら、早めに資格取得を意識しておくのが得策です。
ドローン旅行に資格が必要な理由と二等操縦士の概要
2022年から始まった国家資格制度により、ドローンの操縦士には「一等」「二等」の2種類の免許が用意されました。
そのうち、親子旅行で活用されるのが「二等無人航空機操縦士」という資格です。
二等資格があると、下記のような重要な操作が“申請なし”で可能になります。
| 操作内容 | 資格なしの場合 | 資格ありの場合 |
|---|---|---|
| 人口密集地の飛行 | 国交省の許可が必要 | 許可不要(条件あり) |
| 夜間飛行 | 許可・補助者が必要 | 単独飛行が可能 |
| 目視外飛行 | 原則不可 | 可能(一定条件下) |
つまり、旅先での柔軟な撮影やスケジュールの変更に対応しやすくなり、「親が資格を持っている」というだけで、行動の自由度が一気に広がるのです。



私も実際、夜明けの湖を撮りたいと思ったとき、資格のおかげでスムーズに飛行できました。
資格が不要なケースと旅行時に起こりやすい落とし穴
一方で、すべてのケースで資格が必須というわけではありません。
以下のような条件下であれば、資格がなくても飛行は可能です。
- 100g未満のトイドローンを使う
- 飛行禁止区域ではない
- 人や建物から30m以上離れている
とはいえ、ここには見落とされがちな落とし穴もあります。
例えば「重量100g未満=どこでも飛ばせる」と誤解してしまうと、公園の条例や観光地の管理規定で注意を受ける可能性も。
また、旅行中は天候の変化や人の混雑など、その場で判断を迫られるシーンも多いため、資格を持っていることで“即判断”できる知識と自信が備わります。
親子で資格取得を目指すときの分担と勉強ステップ
親子で資格を取るといっても、同じタイミングで挑戦する必要はありません。
まずは親が先に取得し、安全管理者として機体や制度を把握。
そのあとに子どもが16歳を迎えるころ、一緒に学び直して“ダブル合格”を目指す流れがおすすめです。
- ステップ1:親が国家資格を取得(筆記+実技)
- ステップ2:週末練習で子どもに安全意識と操作を共有
- ステップ3:子どもが16歳になったら、同じ流れで受験へ
私の場合は、古本や使わない機材をメルカリで売って受験費を捻出しました。
夜中にオンライン講座を受講し、早朝にシミュレーターで指慣らし。
そんな努力の過程も、子どもにとっては学ぶ親の背中として伝わっていくのです。
「親子で資格を取る」となると、やはり費用も気になるところですよね。
資格取得にかかる費用の目安や、抑える方法について知りたい方は、こちらの記事を読むと参考になります。


空撮旅行に最適なドローン機材と費用の考え方
ドローン旅行を本格的に楽しむなら、「どの機材を選ぶか」そして「どれくらい費用がかかるか」を事前に整理しておくことが大切です。
特に親子での旅行となると、機材トラブルや予算オーバーは避けたいもの。
この章では、私が実際に使ってきた機材や費用モデルをもとに、準備の目安を具体的に紹介します。
空撮旅行に向いているドローンと選定ポイント
まず基本となる機体選びですが、空撮旅行でのおすすめは重量250g以上・カメラ性能が4K以上のGPS搭載機です。
理由は、安定した飛行・高画質な映像・位置情報による安全管理ができるためです。
ただし、免許不要で飛ばせる200g未満のモデルも、小学生以下のお子さんとの入門には適しています。
- 飛行の安定性:風に強く、ホバリングが安定するGPS付きモデル
- 映像の質:4K撮影+ジンバル搭載なら滑らかな映像が撮れる
- 携帯性:折りたたみ型なら荷物がコンパクトにまとまる



私はDJI Miniシリーズを使っていますが、旅先でバッテリー持ちや収納性が特に助かりました。
子どもの操作用には、スティックが軽めの「練習用サブ機」を別途用意するのも安心です。
持ち物リスト:バッテリー・ケース・予備パーツ
旅行先では予備パーツや充電周りが命綱になります。
特に1日に複数回飛ばす予定なら、バッテリーは最低でも3本持っていくのが基本です。
以下に、我が家の実際の持ち物リストを紹介します。
| カテゴリ | 具体アイテム |
|---|---|
| バッテリー関連 | バッテリー×3、モバイルバッテリー、大容量充電器 |
| 機体保護 | プロペラガード、キャリングケース、防水カバー |
| 撮影補助 | NDフィルター、スマホホルダー、日除けフード |
| 予備品 | 予備プロペラ、予備スティック、メモリーカード(128GB以上) |
また、旅先のコンビニや道の駅では替えが効かないものも多いため、「壊れても困らない」ように多めに持参することをおすすめします。
機材と旅費を含めた親子旅行の費用モデルケース
では、実際に親子でドローン旅行をする場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
以下は、資格取得済みの親と中学生の子どもで2泊3日の空撮旅行をした際のモデルケースです。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| ドローン本体(中級モデル) | 約100,000円 |
| 予備バッテリー・アクセサリ類 | 約20,000円 |
| 交通費・宿泊費(家族2名) | 約60,000円 |
| 食費・入場料・雑費 | 約15,000円 |
初回はやや高く感じるかもしれませんが、機材を一度そろえてしまえば、2回目以降の費用は旅行代だけで済みます。



我が家ではドローン専用の「旅行積立」を毎月して、1年後の旅費+アクセサリ代をまかなうようにしています。
また、予算に不安がある場合は、中古機の購入や助成金制度の活用も検討しましょう。
次章では、出発までのスケジュール管理と、旅行先選びのヒントを紹介します。
家族の予定に合わせたドローン空撮旅行スケジュール例
ドローン旅行は、思いつきでは実現できません。
家族の予定、資格の取得、許可申請、機材の準備……やることは多岐にわたります。
ですが、逆に言えば、段取りさえ押さえれば「安心して飛ばせる旅」を作るのは難しくありません。
6か月で出発を目指す準備スケジュールと管理法
我が家では、長男が「次の夏休みに撮りたい」と言い出したのを機に、逆算スケジュールで6か月前から動き始めました。
そのときに使ったのが、月ごとのToDoリストと、Googleカレンダーによる家族共有です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 6か月前 | 親の資格取得スタート(オンライン講座+教材準備) |
| 4か月前 | 筆記試験合格→実技練習スタート、機体選定 |
| 2か月前 | DIPS申請、宿泊先の予約、子どもの操作練習 |
| 1か月前 | バッテリー準備、持ち物チェック、撮影計画の共有 |
| 出発週 | 機体・充電・保険最終確認、天候チェック |



手帳よりも、家族全員のスマホで予定が見えるGoogleカレンダーが圧倒的に便利でした。
特に試験日やDIPS2.0の提出期限など、「動かせない日付」は早めに決めておくとスムーズです。
天候・季節を活かす旅行先とベストシーズン選び
次に悩むのが「どこへ行くか?」という旅行先の選定です。
ポイントは、「天候×景色×人の少なさ」が揃うタイミングを見つけることです。
撮影テーマ別のおすすめの旅行先と季節は以下の通りです。
| テーマ | 場所の例 | おすすめ時期 |
|---|---|---|
| 紅葉空撮 | 長野・京都・山形の山間部 | 10月下旬〜11月中旬 |
| 海岸線の撮影 | 伊豆・千葉南部・瀬戸内沿岸 | 5月〜6月(風が穏やか) |
| 雪景色 | 北海道・白馬・会津 | 2月中旬(積雪安定) |
夏休み中は人が多いため、早朝や平日を狙うことで、ゆったりと飛ばせる時間を確保できます。
現地での撮影計画とトラブル対処のシミュレーション
旅行に出る前に、現地での撮影計画書をざっくり作っておくのがおすすめです。
「何時にどこで飛ばすか」「誰が何を持つか」「雨が降ったらどうするか」まで、紙でもスマホでもいいので整理しておきましょう。
私がよく使うのは、以下の3パターンの事前想定です。
- 風が強くて飛ばせない場合 → 室内で映像編集タイムに
- 機体が動かない・アプリ不調 → 予備機・別端末を用意
- 近隣に迷惑をかけそう → 早朝に撮影orドローン使用中止



「現地に行ってから考えよう」ではなく、想定外を先に潰しておくことで、当日家族全員が慌てずに動けます。
こうした「シミュレーション文化」こそ、親子で学びながら飛ばす旅に必要な土台です。
次の章では、この経験をどう次のステップにつなげるか、まとめていきます。