ドローンの資格試験に合格したあと、やるべきことは何だと思いますか?
「これで自由に飛ばせる!」と思いきや、実は重要な手続きがいくつも残っています。
国家資格である「無人航空機操縦者技能証明」はあくまでスタートライン。
実際に飛ばすためには、登録申請や保険加入など、安全と法令を守るための準備が必要不可欠です。
私自身も、合格後に機体登録の存在を知って慌ててDIPS2.0を開いたひとりです。
だからこそ、同じように「何から手をつけていいかわからない」という方に、体系的に道筋をお伝えしたいと思います。
この記事では、
- 合格直後にやるべき手続きの全体像
- 登録・保険・技能証明に関する実務的な注意点
- 私が実践したスケジュールと失敗談
などについて、順を追って丁寧に解説していきます。
ドローン資格に合格したら最初にやるべき手続きとは?
無事にドローン国家資格に合格した瞬間、達成感とともに「さあ、飛ばすぞ!」という気持ちが湧き上がるのは当然です。
しかし、実際にはまだ飛行をスタートできません。
なぜなら、操縦資格を取っただけでは法的な準備が不十分だからです。
ここでは、合格後に最初に着手すべき3つの基本手続きを整理してお伝えします。
これらを終えて初めて、安全かつ合法に飛行が可能になります。
操縦資格だけでは足りない3つの必須手続き
国家資格である「二等無人航空機操縦士」は、ドローンを飛ばすための“免許証”のようなもの。
しかし、それだけでは機体を飛ばす許可にはなりません。
- 機体登録(無人航空機登録システム=DIPS2.0)
- 技能証明書の申請(合格後に申請・発行される)
- 保険加入(万が一の事故への備え)
この3つの手続きがそろって、ようやく空を合法的に飛べる状態になります。

私も最初は「合格すれば終わり」と思っていましたが、実際には登録すらしていない状態で飛ばそうとして、危うく無登録飛行になるところでした。
無人航空機の登録方法と法的義務のポイント
2022年6月から、100g以上の無人航空機は「機体登録」が義務化されました。
機体登録せずに飛ばすと、航空法違反で罰則の対象になります。
機体登録は国土交通省の「DIPS2.0」というオンラインシステムを使って行います。
機体ごとに登録番号が割り当てられ、リモートIDも付与されます。
- 100g以上の機体はすべて登録必須
- 登録しないまま飛ばすと1年以下の懲役または50万円以下の罰金
登録された機体には、登録記号を記載したシールを貼り、必要に応じてリモートIDの発信機能を有効にする必要があります。
合格後の申請で失敗しないためのタイムライン
ドローン資格試験に合格したら、できるだけ早く下記の手順で動き始めることをおすすめします。
- 合格通知を受け取る
- 技能証明書の申請手続きをDIPS2.0で開始
- 機体登録を並行して進める(未登録でも申請は可能)
- 登録完了後、機体に登録記号を表示
- 保険に加入し、飛行前にすべての書類を整える
このように、「資格取得」→「登録」→「保険」という流れをセットで考えるとスムーズです。



私は証明書の申請と機体登録を同時に進めたことで、実技試験の翌月には実飛行に移れました。
無人航空機(ドローン)の登録申請と技能証明書の取得手順
資格に合格したあと、実際に飛ばすためには「無人航空機の登録」と「技能証明書の取得」が必須となります。
この2つの手続きは、すべて国土交通省のオンラインシステム「DIPS2.0」から行えます。
ここでは、その具体的な流れと注意点を段階ごとに解説します。
DIPS2.0を使った登録申請の具体的な流れ
DIPS2.0とは、「Drone Information Platform System」の略称で、ドローンの登録や技能証明の管理、飛行許可の申請までを一元管理できる国の公式システムです。
登録申請の流れは次のとおりです。
- GビズID(またはマイナンバーカード)でログイン
- 機体情報の登録(メーカー名、型番、シリアルナンバーなど)
- 本人確認書類(運転免許証など)のアップロード
- 登録手数料の支払い(オンライン決済)
登録が完了すると、機体ごとに登録記号(英数字)が発行され、PDF形式でダウンロードできます。
この記号は機体に明記しなければなりません。
- インターネット接続環境
- GビズIDまたはマイナンバーカード(ICカードリーダー)
- ドローン本体の情報(型番、製造番号など)
- 本人確認書類(写真付き)
初めての方は、GビズIDの取得に数日かかる場合もあるため、早めに準備しておくことをおすすめします。
技能証明書が届くまでの日数と注意点
試験に合格しても、技能証明書が発行されるまでには申請から2〜4週間程度かかるのが一般的です。
その間に機体登録や保険加入の準備を進めておくとスムーズです。
証明書は原則として「紙のカード形式」で郵送されます。
申請時に登録住所や本人情報に誤りがあると、届かない・遅れるといったトラブルも起きるので注意しましょう。



私も実際、番地の表記ミスで1週間以上到着が遅れました…意外と細かい部分が重要なんです。
未登録飛行がもたらす違反リスクと罰則例
ここで強調したいのは、登録や技能証明を怠った状態で飛行させた場合、法的リスクが非常に高いということです。
未登録のまま飛行すると、航空法違反で最大50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、事故を起こした場合、保険に未加入であると損害賠償の全額を自費で負担することになりかねません。
つまり、資格を取っただけでは「責任を果たした」とは言えないのです。
安全と信頼を守るためにも、登録・証明・保険は三位一体で行う必要があります。
ドローン保険の選び方とリスク対策の考え方
ドローンを飛ばす上で、もうひとつ大事な要素が保険の加入です。
資格を持ち、機体登録を終えていても、事故が起これば重大な損害や責任が発生します。
だからこそ、保険は「任意」とはいえ実質的には必須と考えるべきです。
ここでは、保険の種類ごとの特徴や費用、親子で飛ばすときの選び方についてご紹介します。
対人・対物・機体の各保険の特徴と必要性
ドローン保険には、主に以下の3種類があります。
| 保険の種類 | 対象とする損害 |
|---|---|
| 対人賠償責任 | 人にケガをさせた場合の医療費・損害賠償 |
| 対物賠償責任 | 車や建物、第三者の物を壊した場合 |
| 機体損害 | 自身のドローンが破損・墜落した場合 |
最低限、「対人・対物賠償」のセットには加入するのが安全な選択です。
機体損害は任意ですが、機体が高価であれば検討する価値があります。



私は初期のうちは対人・対物のみ加入していましたが、長男が墜落させたことで機体破損も対象に入れるようになりました。
保険の種類や補償内容について、さらに具体的に知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。


保険料の相場と補償内容の比較ポイント
ドローン保険は種類も多く、個人向け・事業向けで費用や補償範囲が異なります。
以下は、個人が飛行を前提とした保険の大まかな相場です。
| 補償内容 | 年間保険料の目安 |
|---|---|
| 対人・対物(1億円) | 5,000円〜8,000円 |
| 機体損害(上限30万円) | +5,000円〜10,000円 |
| 副業向けフルカバー | 15,000円〜30,000円 |
- 飛ばす頻度が少ないなら安価なプランでも可
- 家族で使う場合は補償対象者に「親族」も含まれるかを必ず確認
- 副業や撮影代行を視野に入れるなら、業務使用可のプランが必要
「使う頻度」と「壊れたときのダメージ感」で、保険の厚みを決めていくのがコツです。
個人・親子・副業目的で使えるおすすめ保険会社
現在、ドローン保険を提供している主な会社には以下のような選択肢があります。
| 保険会社 | 特徴 |
|---|---|
| 東京海上日動 | 業務用途向け。副業や空撮ビジネスにも対応 |
| 楽天損保「ドローン保険」 | 個人向けで費用が手ごろ。対人・対物が標準 |
| 三井住友海上 | 家族での利用にも配慮あり。オプションも豊富 |
| DJI Care Refresh | DJI製品専用。機体破損に特化し交換対応あり |
私の場合は、まず楽天損保で基本的な対人・対物に入り、のちに副業申請をしたとき東京海上に切り替えました。
どこまでをカバーしたいかを最初に整理しておくと、選びやすくなります。
ドローン登録・保険加入に必要な書類と情報一覧
いざ登録や保険の手続きをしようとしたとき、「あの情報どこにあったっけ?」と慌てた経験はありませんか?
とくに初めての場合は、何が必要でどこにあるのか探すだけで時間がかかってしまいます。
この章では、無人航空機の登録や保険加入に必要な書類と情報を一覧形式で整理します。
準備が整っていれば、手続きはオンラインでスムーズに進められます。
無人航空機の登録時に必要な書類チェックリスト
DIPS2.0を使って無人航空機を登録する際に必要な書類や情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| GビズIDまたはマイナンバー認証 | 本人認証のために必要。GビズIDは数日かかる |
| 機体情報 | メーカー名、型番、製造番号、重量など |
| 機体の写真(必要な場合) | 外観が確認できる写真をアップロード |
これらを事前に1つのフォルダにまとめておくと、登録作業がぐんとラクになります。



私は製造番号の写真を探すのに手間取り、登録完了まで半日かかってしまいました。ラベルは最初に撮っておくと安心です。
保険申し込みに必要な情報と取得方法
ドローン保険の申し込み時には、以下のような情報が必要になります。
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 契約者情報 | 氏名、住所、電話番号など |
| 飛行場所・目的 | 個人使用か業務使用か。対象エリアの指定が必要な場合も |
| 機体情報 | 登録番号や型番。機体損害を含む場合は必須 |
| 飛行回数の目安 | 年に何回飛ばすか、おおまかな頻度 |
- 機体登録と保険申し込みは同時並行で進めると効率的
- 複数の保険会社の見積もりフォームで「必要項目」を事前チェック
- 契約書類はPDFで保存し、スマホやクラウドでも閲覧できるようにしておく
保険によっては「飛行の目的」によって保険料が変わることもあるため、正直に記載することが重要です。
各手続きにかかる日数と効率的な進め方
資格合格から実際に飛行可能になるまでに、各ステップで必要な日数は次の通りです。
| 手続き | 所要日数の目安 |
|---|---|
| GビズID取得 | 3〜5営業日 |
| 機体登録(DIPS) | 即日〜2日(内容による) |
| 技能証明書の申請 | 2〜4週間 |
| 保険加入 | 即日〜3日(会社による) |
これらを同時進行で進めることが、効率化のカギとなります。
特に、GビズIDの取得には時間がかかるため、資格試験の合格前から準備しておくのもおすすめです。
ドローン試験合格後にやること一覧!やり忘れゼロの行動マップ
ここまで読んで「けっこうやること多いな…」と感じた方もいるかもしれません。
でも大丈夫です。
大切なのは、ひとつずつ順番に進めること。
この章では、合格後に何をいつ、どの順番でやるべきかを時系列でマップ化してご紹介します。
合格日から飛行許可取得までの行動スケジュール
ドローン資格合格後、最短で飛行許可を得るまでの流れを、実際のタイムラインに沿って見ていきましょう。
| 時期 | 行動内容 |
|---|---|
| 合格当日 | 技能証明の申請開始(DIPS2.0) |
| 1〜3日目 | GビズID取得申請/本人確認書類の準備 |
| 4〜7日目 | 無人航空機登録の申請(機体情報と証明書のアップロード) |
| 1週間後 | 保険加入手続き(同時進行が望ましい) |
| 2〜4週間後 | 技能証明書到着→本番フライトへ |
- Step1:証明書申請
- Step2:GビズID準備+登録申請
- Step3:保険加入と登録番号の取得
- Step4:書類確認して初飛行へ
すべてを一気にやる必要はありません。
1日1つ、確実に進めれば、1カ月以内に安全・合法な飛行が実現できます。



我が家では、カレンダーに「今日は保険」「今日は登録」と書いて貼り出しました。家族の理解と応援があると進みやすいです。
まとめ:ドローンを安心して飛ばすためのスタートは合格後の手続きから
ドローン資格に合格した瞬間は、「これで空を飛べる!」という期待感にあふれていますよね。
でも本当のスタートは、そのあとにどんな準備をするかにかかっています。
登録・保険・証明…すべてが揃ってこそ、安全で合法な飛行が実現するのです。
これから資格取得を目指す方は、効率的な合格ルートを知っておくと安心です。
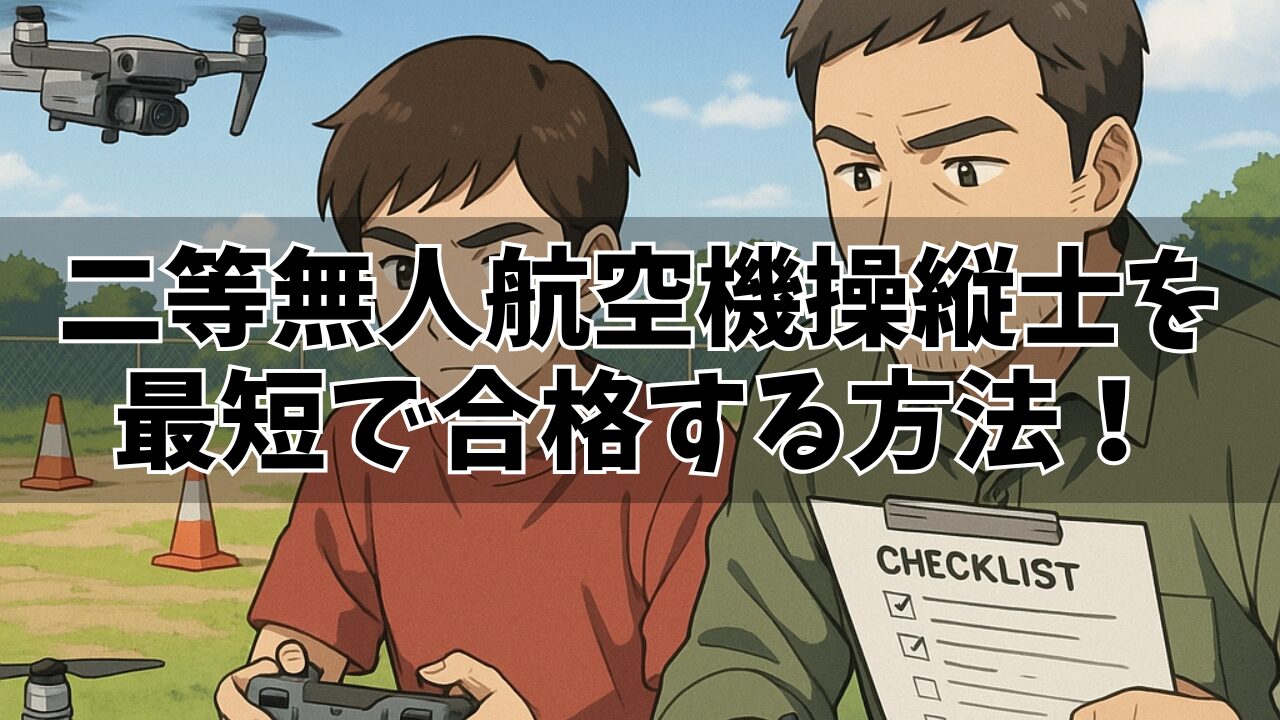
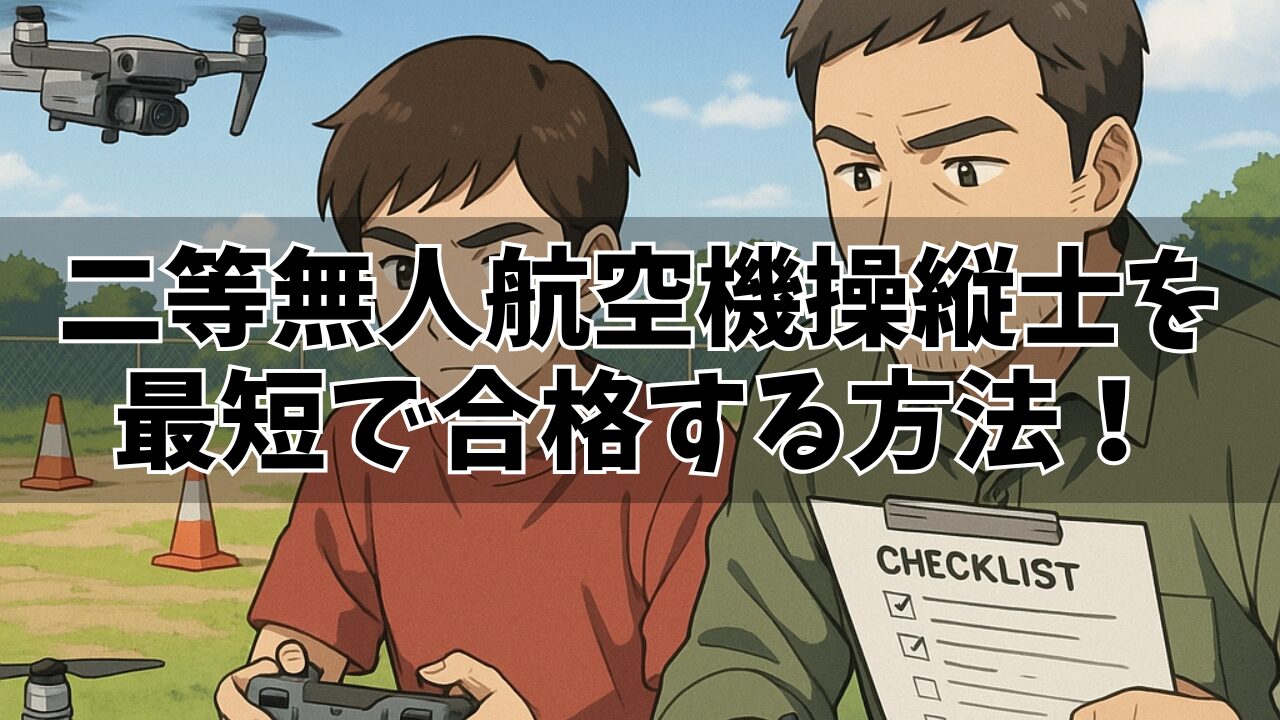
今すぐ着手すべき3つの行動
合格直後のタイミングで、ぜひ取り組んでほしいアクションが3つあります。
- DIPS2.0にログインして、技能証明書の申請を開始する
- GビズIDや本人確認書類を準備し、機体登録の下準備を整える
- 保険会社の候補を3つほど調べて、補償内容を比較してみる
この3ステップを今日中に済ませるだけでも、他の人より一歩リードできます。



私も「夜にDIPSを開いただけ」で、次の日には登録申請が完了しました。行動の第一歩って、意外と簡単なんです。
家族や仲間と共有できる手続きロードマップ
ドローンの手続きは、ひとりで抱え込まず、家族や仲間と分担・共有して進めるのが理想です。
特に親子でドローンを楽しむなら、親が主導して「こうやって飛ばす準備を整えるんだよ」と見せることが、子どもの学びにもつながります。
- 週末に「手続きタイム」を30分だけ設ける
- ToDoリストを冷蔵庫などに貼って見える化する
- 子どもと一緒にDIPS画面を見ることで、制度への理解も深まる
“飛ばすこと”だけでなく、“飛ばすための準備”にも家族で関わることで、ドローンのある生活がより豊かになります。
資格を取った今がチャンス。
ひとつひとつ準備を整えながら、親子で空を共有できる日を目指しましょう。







